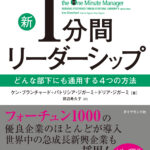介護現場におけるハラスメント対策(1)
はじめに
「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」は、厚生労働省老人保健健康増進等事業の一環として作成されたガイドラインです。このマニュアルは、平成30年度に「介護現場におけるハラスメントに関する調査研究事業」(実施団体:株式会社 三菱総合研究所)により作成され、令和元年度には「管理者及び職員を対象にした研修のための手引き」、令和2年度には「介護現場におけるハラスメント事例集」が追加されました。これらは、介護現場でのハラスメント防止に向けた具体的な対策や方針を提供し、職員が安心して働ける環境を整えるための重要なツールです。【参照元】 厚生労働省 介護現場におけるハラスメント対策
本コラムでは、この「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」を参照しながら、介護現場におけるハラスメント対策について詳しく解説していきます。
ハラスメントの定義と背景
ハラスメントとは何か
ハラスメントについて、確定した定義はありませんが、一般的にハラスメントとは、相手の人格や尊厳を傷つける言動や行動を指し、その行為が継続的に行われることによって相手に精神的、肉体的な苦痛を与えるものをいいます。介護現場におけるハラスメントには、上司から部下へのパワーハラスメント、同僚間のモラルハラスメント、利用者やその家族からのハラスメントなどが含まれます。
このハラスメント対策マニュアルでは、具体的には、介護サービスの利用者や家族等からの、以下のような行為を「ハラスメント」と総称しているようです。
1)身体的暴力:身体的な力を使って危害を及ぼす行為。
例:コップを投げつける/蹴られる/唾を吐く
2)精神的暴力:個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。
例:大声を発する/怒鳴る/特定の職員にいやがらせをする/「この程度できて当然」と理不尽なサービスを要求する
3)セクシュアルハラスメント:意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為。
例:必要もなく手や腕を触る/抱きしめる/入浴介助中、あからさまに性的な話をする
介護現場でハラスメント対策が必要と言われている背景
介護現場は独特の環境を持ち、ハラスメントが発生しやすい要因がいくつか存在します:
- 高ストレス環境
- 利用者の身体的ケアと心理的サポートの両立
- 職員の精神的負担が大きい
- 業界特有の課題
- 慢性的な人手不足
- 職員の多忙さ
これらの要因が重なり、職場環境の悪化とハラスメントリスクの上昇につながっています。
なお、介護現場におけるハラスメントは、「1.職場内でのハラスメント」「2.利用者・家族等からのハラスメント」の大きく二つに分類されますが、これらは異なる性質を持つため、別々の対策が必要とされています。
平成30年度の厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護現場における利用者や家族等によるハラスメントの実態調査」による調査結果は、介護現場におけるハラスメントの深刻さを浮き彫りにしています
- 利用者からのハラスメント経験者:4~7割
- 家族等からのハラスメント経験者:1~3割
ハラスメントの種類
- 身体的暴力
- 精神的暴力
- セクシュアルハラスメント
サービス種別による差
- 最も多いケース:約6割の職員が経験
- 最も少ないケース:約2割の職員が経験
すべてのサービス種別で、一定数のハラスメント被害が報告されています。この現状を踏まえ、介護現場における包括的なハラスメント対策の実施が急務となっています。
ハラスメント対策はなぜ必要なのか
職場環境の改善のため
ハラスメント対策は、職場環境の改善に直結します。ハラスメントが放置されると、職員の士気が低下し、離職率が上昇するだけでなく、利用者へのサービスの質も低下します。逆に、ハラスメントのない健全な職場環境を作ることで、職員の働きがいが向上し、利用者に対するサービスの質も向上します。
事業主の安全配慮義務のため
事業者(事業主)は、労働契約法に定められる職員(労働者)に対する安全配慮義務等があることから、その責務として利用者・家族等からのハラスメントに対応する必要があります。
利用者が介護サービスを継続的かつ円滑に利用できるようにするため
ハラスメント対策は介護職員を守るだけではありません。ハラスメントを行っている利用者・家族等の中には、著しい迷惑行為を行っていると認識していない人がいると考えられます。心身が不安定な人もいることにも留意する必要があります。
しかし、ハラスメントの発生の有無は、利用者等の性格・状態像によって左右されるものではなく、客観的に判断し、再発防止策を講じることが必要です。それにより、利用者にとっても継続的に介護サービスが円滑に利用できます。
ハラスメントのリスク要因
環境面でのリスク要因
介護現場の物理的な環境もハラスメント発生のリスクを高める要因となります。例えば、職員数に対して利用者数が多すぎる場合や、十分な休憩が取れない労働環境は、職員のストレスを増加させ、ハラスメントの発生につながる可能性があります。
利用者に関するリスク要因
利用者の身体的・精神的な状態が悪化することで、職員に対する要求が過度に厳しくなる場合があります。これが職員にとってハラスメントと感じられることがあり、利用者のケアを行う上での大きなストレス要因となります。
サービス提供側のリスク要因
職員間のコミュニケーション不足や、管理職のリーダーシップ不足もハラスメントのリスク要因です。職場内での対話が不足していると、誤解や摩擦が生じやすくなり、これがハラスメントに発展することがあります。
まとめ
介護現場におけるハラスメント対策は、職員の働きやすさと利用者へのサービスの質を向上させるために不可欠です。ハラスメントの放置は職場環境を悪化させ、職員の離職やサービスの質低下を招くため、迅速かつ適切な対策が求められます。
特に、組織全体での取り組みや問題の共有が重要です。
ハラスメント対応、“誰に相談するか”で結果は大きく変わります
ハラスメント対応において、誰に相談するか――それが、事態を沈静化させるか、さらに悪化させるかの分かれ道になります。
ハラスメントに関する知識が乏しく、対応経験の少ない社会保険労務士に任せたことで、かえって職場が混乱し、深刻な「二次被害」が生じたケースは、決して珍しくありません。
たとえば、こんな対応が現場で行われています。
相談者の意向や心身の状況を確認しないまま、「加害者」と決めつけてヒアリング
行為者を吊し上げるような対応をしてしまい、チーム内の信頼関係が崩壊
記録もなく、対応のプロセスが曖昧なため、後々「隠蔽だ」と誤解される
結果的に被害者も行為者も退職、残った職員が「誰にも相談できない」と萎縮
これらは、いずれも“悪意のない失敗”です。
しかし、知識や経験の不足による初動のミスが、被害者の孤立や、行為者の不信感を生み、現場全体に二次被害を拡大させてしまうのです。
当事務所の強み|「ハラスメント防止コンサルタント」資格者が対応します
当事務所では、厚生労働省委託事業に基づく「ハラスメント防止コンサルタント」の資格を有する社会保険労務士が、相談窓口の運用から初動対応、記録整備、再発防止策の設計まで一貫して対応いたします。
被害者(相談者)への傾聴と希望の確認
行為者にも配慮した公平・中立なヒアリング
厚労省ガイドラインや判例に基づく判断軸の提示
職場の空気を整え直す、実践的な改善プランの提案
「人を守る」だけでなく、「組織を守る」視点で動けることが、当事務所の特徴です。
詳しくは本ホームページ「ハラスメント防止対策」のページをご覧ください。