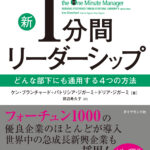顧問社労士・顧問弁護士が「ハラスメント外部相談窓口」であることの根本的リスク

「外部相談窓口は、いつもの社労士の先生にお願いしよう」
「顧問弁護士がいれば安心だよね」
そう考える経営者は少なくありません。むしろ、「顧問がいる」という事実自体に、どこか安堵しているケースもあります。しかし、その“安心感”こそが、ハラスメント対応における最大の落とし穴になり得るのです。
実際に、ある施設では、パワハラに悩んでいた職員が外部相談窓口の設置を知り、「救われた」と思ったのも束の間、その窓口が「普段から経営者と頻繁に連絡を取っている顧問社労士」であると知った瞬間、声を上げることを諦めてしまいましたということを聞いたことがあります。
このようなケースは決して稀ではありません。では、なぜこうした事態が生じるのか。その背景には、“利益相反”という本質的な構造問題が存在しています。
利益相反のジレンマ
「中立」ではいられない、顧問という立場
顧問社労士や顧問弁護士は、その職責上、企業側の立場を守る契約関係にあります。契約書には明文化されていなかったとしても、実務上の役割としては「企業寄り」であることがほとんどです。
だからこそ、仮に職員が深刻な被害を受けていたとしても、その相談内容が「経営者の不適切な対応」や「内部体制の不備」を指摘するものであれば、顧問は非常に難しい立場に立たされることになります。
たとえば、あるケースでは、施設長による継続的な高圧的言動が問題となりました。しかし、外部相談窓口である顧問弁護士は、過去にその施設長の労務トラブルも肩代わりしており、「今さら指導対象にするのは難しい」と口を濁してしまったのです。
このように、顧問が相談窓口を兼ねることで、経営者と職員のあいだにある“緊張関係”がそのまま持ち込まれ、結果として機能不全に陥る恐れが高まります。
信頼関係が強固であるほど危険?
皮肉なことに、経営者と顧問との信頼関係が強ければ強いほど、職員にとっては「話せない相手」となってしまいます。顧問が「社長の右腕」と見なされている場合、その人物に自分の上司のハラスメントを告発することが、どれだけの心理的負担になるか、想像に難くありません。
相談者が望んでいるのは“処分”ではなく、“理解”と“安心”です。しかし、その第一歩である「話すこと」すら選べない環境では、相談体制は形骸化し、問題は深く静かに潜行してしまいます。
「誰のための相談窓口か」を問い直す
形式だけの外部窓口が生む“見えない加害”
ある高齢者施設で、夜勤職員が長期にわたって上司の無視や理不尽な指示に悩んでいました。業務時間外に「掃除が足りない」とLINEで叱責される、会議で意見を言えば遮られる——だが、表面化はしていませんでした。
この職員が外部相談窓口の案内を見て「ようやく話せる」と思った矢先、そこに記載されていたのは、顧問社労士の連絡先。日頃から経営陣と打ち合わせしている相手だとわかり、彼女はそっと案内を閉じました。
これは“相談窓口を設けないよりも悪い状態”です。なぜなら、「制度があるのに助けを求められなかった」という事実が、職員の無力感や不信感を一層深めるからです。相談する自由を奪うことは、黙ったまま傷つくことを強いる“見えない加害”につながりかねません。
外部窓口の機能不全は、施設の信頼失墜に直結
もし、このような体制がマスコミやSNS等で告発されたら、組織のダメージは計り知れません。制度は形だけ、相談は機能しない、顧問は経営の味方だけ——そういった印象が一度広がってしまえば、利用者からも、職員からも、信頼を取り戻すのは困難です。
しかも、そうした体制の不備は、コンプライアンス違反や訴訟リスクの引き金にもなり得ます。相談に適切に対応できなかったこと自体が、安全配慮義務違反などに問われる可能性もあるのです。
外部相談窓口に求められる「条件」とは
独立性・実務性・そして“寄り添い力”
外部相談窓口に最も必要なのは、「中立性」や「独立性」だけではありません。
・労務トラブルへの正確な知識
・ハラスメントの構造理解
・組織文化や人間関係への配慮
こうした要素がすべて揃っていなければ、職員の声を受け止めることはできません。ただの「受付窓口」ではなく、「関係をつなぎ直すきっかけ」としての機能が求められているのです。
顧問とは別の立場だからこそ、できることがある
当事務所では、企業や福祉施設から「相談体制の見直し」についての相談を多く受けています。そこで強く感じるのは、顧問と窓口の分離が現場の安心感につながるという事実です。そのため、当事務所では顧問先に対しては「ハラスメント外部相談窓口」を請け負うことはやっておりません。
顧問は経営の助言役、外部窓口は職員の声を汲み取る第三者。役割を切り分けることで、双方の機能が最大限に活かされ、組織全体の健全性が高まります。
まとめ|相談窓口の体制は、企業の“対外的な誠実さ”そのもの
「声を聴く覚悟」が問われている
相談窓口は、単なる苦情受付ではありません。そこには、人の尊厳を守る責任と、組織が自らの姿勢を問われる覚悟が必要です。
顧問社労士や弁護士の“便利さ”だけで体制をつくってしまうと、その「便利さ」が企業を守る盾にも、傷ついた人を追い詰める刃にもなりかねません。
どこまで声を聴く気があるか。
その声に、どう応える気があるか。
それこそが、いま求められている経営の本質です。
当事務所の支援
実務と倫理のバランスを備えた外部窓口体制を
当事務所では、ハラスメント防止コンサルタントとして、独立した外部相談窓口の設計・導入支援を行っております。介護・福祉・医療業界における豊富な支援実績を活かし、「現場の声が届く体制づくり」をご提案しています。なお、先にも述べた通り、当事務所では顧問先に対しては「ハラスメント外部相談窓口」を請け負うことはやっておりません。
「いまの体制で本当に大丈夫か?」
「制度はあるが、誰も利用していない」
「第三者の視点で見直したい」
そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。制度を整えることが目的ではなく、人の声が届く仕組みをつくることを、私たちは何より大切にしています。