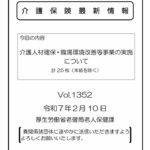介護人材確保・職場環境改善等事業Q&A(第2版)が公開されました
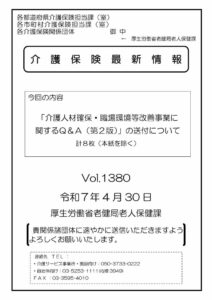 令和7年4月30日、厚生労働省老健局より「介護保険最新情報Vol.1380」が発出され、「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第2版)」が公表されました。
令和7年4月30日、厚生労働省老健局より「介護保険最新情報Vol.1380」が発出され、「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第2版)」が公表されました。
本稿では、全26問のQ&Aを読み解きつつ、介護事業者や中小企業の経営者・人事担当者が押さえておくべきポイントを整理し、当事務所としての見解を提示いたします。
介護人材確保・職場環境改善等事業とは?
2023年度補正予算に基づき創設された本事業は、介護現場の人材確保と職場環境の改善を通じて、定着率の向上および介護サービスの質の向上を目指すものです。
- 補助対象は、介護サービス事業所における一時金等の人件費改善および職場環境改善に要する経費。
- 原則として令和6年12月を基準月とし、令和7年1月〜3月も選択可能。
- 対象は、介護職員を中心としつつ、実態として従事している本部職員や事業所全体の従業員も含めることが可能です。
Q&A一覧
Q1. 補助金の実施時期はいつまで?
補助額による人件費の改善や職場環境改善は、基準月(令和6年12月を基本とし、令和7年1月、2月又は3月も選択可能)から各自治体が定める実績報告書の提出までに行う必要があります。 そのうち、当該人件費の改善は、介護事業所に対する緊急支援という趣旨を鑑み、可能な限り速やかに実施していただきたいとのことです。
Q2. 法定福利費の増加分は人件費改善に含めてよいか?
含めることが可能です。本来、人件費の改善は、従業員への一時金等への支給に充てるものですが、人件費の改善に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることも可能です。
Q3. 介護職員以外にも支給できる?
介護職員への配分を基本ですが、同一事業所において雇用する者であれば、介護職員以外も含め、すべての職員に配分可能です。
Q4. 本部職員(法人本部などの介護に従事しない職員)は対象になるか?
介護事業所の業務に従事していれば対象。ただし、この補助金の対象となっていない事業所所属職員は不可。
Q5. ベースアップに使える?
一時金等が基本です。恒久的な支援策ではないため、ベースアップに充てることは想定していないとのことですが、各事業所の経営判断として、将来的な賃上げを見越した「つなぎ」として用いるのは妨げるものではありません。
Q6. 配分ルールはある?
人件費と職場環境改善費の配分ルールは特に設けられていません。全額をどちらかに充てることも可能です。
Q7. 加算の算定時期の要件は?
基準月に介護職員処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)を算定していることが基本。未対応でも4月からの体制届があれば対象。
Q8. 加算Ⅴのみ算定している場合は?
原則対象外。ただし、、この場合であっても、問7に記載のとおり、令和7年4月から処遇改善加算の算定に向けた体制届け出を期日までに行っている場合には、対象になります。
Q9. 休廃止予定の事業所は?
事業計画書時点で休廃止が明らかなら対象外。後から休廃止する場合は都道府県へ速やかに届け出ること。
Q10. 介護職員の求人経費に使えるか?
「介護助手等」の募集経費に限定。介護職員の一般的な募集経費には充てられません。なお、「介護助手等」の「等」には、「介護補助者」、「介護サポーター」など、介護助手に類する者を想定しています。
Q11. 過去に要した費用は対象か?
対象外です。基準月以降の支出のみが補助対象です。
Q12. 入金前の支出は対象か?
基準月以降の実施であれば、入金前でも補助対象として報告可能です。
Q13. ICT機器への充当は可能か?
不可。ICT導入・協働化支援事業の事業所負担分も含め、本補助金は充当不可です。、この経費における事業所持ち出し分について本補助金の対象とすることはできません。
Q14. 職場環境改善経費について、介護助手等を募集するための経費や研修費以外に、どんな経費が職場環境改善に該当?
職場環境改善経費については、介護助手等を募集するための経費又は職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費に充当することを基本です。
なお、「介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化」、「業務改善活動の体制構築」、「業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組」に関する取組を実施するために要する費用のうち、専門家の派遣費用や会議費等に充当することも可能です。
ただし、介護テクノロジー等の機器購入費用などは不可。
Q15. 基準月は事後的に変更できる?
不可。申請後の基準月変更は認められません。
Q16. 12月以外を選んだ理由の届出は必要?
不要。ただし、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分を適切に反映するとともに、基準月の選択誤りなどの事務的な誤りを防ぐ観点からも、原則、令和6年12月サービスを基準月とすることが望ましい。
Q17. 過誤調整分の取り扱いは?
令和7年3月末までに発生し、4月10日までに受理されたものに限り反映されます。
Q18. 令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象か?
令和7年4月以降開設の事業所は補助金の対象外です。
Q19. 債権譲渡できる?
不可。登録された事業所または法人の口座に直接振込されます。
Q20. 法人単位で申請可能か?
法人単位で計画書の作成は可能。ただし申請は事業所の都道府県単位で行う必要があります。
Q21. 職場環境改善経費として、テクノロジー機器購入費は?
不可。介護テクノロジー等の機器購入には本補助金は充当できません。
Q22. 職場環境改善経費として、PC端末等の購入は?
対象外です。テクノロジー関連の物品購入は不可です。
Q23.事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合において、廃止前の事業所として補助金を申請し、新規に指定を受けた事業所において補助金を活用することは可能?
職員や業務が実質的に継続していれば可。変更届と様式2-3の提出が必要です。
Q24. 研修費には何が含まれる?
講師謝金、旅費、資料代、印刷費、受講料など、明確に研修目的と分かる費用が対象です。
Q25. 求人広告費や紹介料は?
介護助手等に限定して、求人広告・チラシ・紹介料等が補助対象です。
Q26. 使途の途中変更は可能か?
可能。事後的な変更も実績報告時に反映すればよく、計画書の再提出は不要です。
当事務所の見解と提案
今回のQ&A第2版では、補助対象の明確化とともに、事業者が柔軟に運用できる余地が多く示されました。一方で、ICT機器購入のように「対象外」と明記された費目や、加算の算定要件の取り扱いなど、注意が必要な点も明らかです。
特に注目すべきは以下の3点です:
- 補助対象の「範囲」の緩やかな拡大:介護職員以外への支給、法人本部職員の対象化など、現場の実情に沿った柔軟な設計が意識されています。
- 事務負担軽減に配慮された運用:事後的な使途変更を許容する方針は、現場にとって大きな負担軽減につながります。
- 戦略的な活用が問われる補助金設計:一時金支給にとどまらず、将来の賃上げへの橋渡しとして制度を活用する視点が重要です。
介護人材の定着と生産性向上を同時に実現するには、単なる支給額の確保では不十分です。補助金の“使い道”と“設計思想”が問われる時代に入ったとも言えるでしょう。
当事務所では、事業計画書の作成や加算対応はもちろん、採用戦略、人件費設計、研修設計にいたるまで総合的な支援が可能です。制度に振り回されるのではなく、制度を活かして現場を前に進めたいとお考えの皆さまは、ぜひ一度ご相談ください。
【参考資料】介護保険最新情報Vol.1380(PDF)