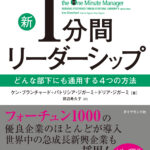休職・メンタルヘルス|「メンタル不調かも?」と感じた職員に、医師の受診を強制できますか?
結論から申し上げますと、原則として、本人の明確な同意なく医師の受診を強制することはできません。
しかし、医療・介護・福祉の現場では、職員の心身の健康状態が、利用者様の安全やサービスの質に直接影響を与える極めて重要な問題です。そのため、事業主には労働契約法第5条に基づく「安全配慮義務」が課せられており、職員の健康状態を適切に把握し、必要な措置を講じる責任があります。
この「受診の自由」と「安全配慮義務」のバランスをどう取るかが、実務上の重要なポイントとなります。以下に、法的根拠と具体的な対応策を解説します。
法的根拠と原則的な考え方
ご認識の通り、労働者に一方的に受診を「命令」することは、原則として認められません。本人が受診を拒否しているにもかかわらず、無理強いすればパワーハラスメントと受け取られるリスクもあります。
ただし、事業主には労働者の健康状態を把握する手段として、労働安全衛生法で以下のような制度が定められています。
一般健康診断(労働安全衛生法第66条第1項)
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に実施する義務があります。これは業務命令として実施できます。ただし、これは身体的な健康状態の把握が主目的です。
産業医等による面接指導(労働安全衛生法第66条の8、第66条の9)
長時間労働(時間外・休日労働が月80時間超など)により疲労の蓄積が認められる労働者が、自ら申し出た場合に実施が義務付けられています。事業主から一方的に命じることはできません。
例外的に「受診命令」が認められる可能性
判例では、特定の状況下において、就業規則に定めがあることを前提に、例外的に業務命令としての受診命令が有効とされるケースがあります。(例:電電公社帯広局事件 最判昭61.3.13)
受診命令が有効と判断される可能性のある要素は以下の通りです。
就業規則上の明確な根拠規定の存在
「事業主は、職員の心身の状況に異常が疑われる場合、専門医の受診を命じることがある。職員は正当な理由なくこれを拒んではならない」といった規定が就業規則に明記されていることが大前提です。
受診を命じる客観的・合理的な必要性
単なる「様子がおかしい」といった主観的な判断ではなく、以下のような客観的な事実に基づいている必要があります。
勤怠の乱れ: 遅刻、早退、欠勤の急増や、連絡のない無断欠勤。
業務遂行能力の著しい低下: これまでなかったようなミスや事故の多発、利用者からのクレームの急増、業務遂行に支障をきたすほどの集中力の欠如。
言動の明らかな変化: 他の職員や利用者様への攻撃的な言動、支離滅裂な発言、極端にふさぎ込むなど、周囲が明らかに異常と認識できる状態。
医療・介護・福祉業界の特殊性
職員の不調が、利用者様の生命・身体の安全に直接的な危険を及ぼす蓋然性(可能性)が高い場合は、事業主の安全配慮義務がより重く解釈され、受診命令の必要性が認められやすくなる傾向があります。
医療・介護・福祉業における実務対応のポイント
上記の法的側面を踏まえ、現場では以下のステップで慎重に対応を進めることが重要です。
対応のステップとポイント
Step 1:客観的な事実の記録と観察
まずは管理監督者が、当該職員の勤怠状況、業務上のミス、言動の変化などを客観的な事実として具体的に、かつ時系列で記録します。「〇月〇日、利用者A様への配薬を間違えそうになり、同僚Bが指摘し事なきを得た」「〇月〇日以降、週に2~3回の遅刻が続いている」など。この記録が、後の面談や判断の重要な根拠となります。
Step 2:丁寧な面談と「受診勧奨」
プライバシーに配慮できる個室で、管理監督者や人事担当者が面談を行います。
point 1: 決して問い詰めるのではなく、「最近、〇〇という状況が続いているけれど、何か困っていることはないか?」「あなたの体調が心配です」と、心配している気持ち(Iメッセージ)を伝えます。
point 2: 産業医面談や、事業所が契約しているEAP(外部相談窓口)など、本人が相談しやすい選択肢を複数提示し、まずは**「相談」**を促します。
point 3: 「診断を受けないと勤務継続できない」といった圧力的な言い方は、本人の心を閉ざし、事態を悪化させるため絶対に避けてください。
Step 3:本人が受診を強く拒否した場合
①業務に大きな支障が出ていない場合
本人の意思を尊重し、無理強いはしません。ただし、「何かあればいつでも相談してほしい」と伝え続け、丁寧な経過観察と声かけを継続します。
②業務や利用者様の安全に具体的な支障・危険が生じている場合
就業規則の規定を確認した上で、再度面談の場を設けます。
記録した客観的事実を具体的に示し、「このままの状態では、あなた自身の健康だけでなく、利用者様の安全を守るという私たちの最も重要な責務を果たすことが難しくなる。まずは、専門医の意見を聞いて、会社としてどのようなサポートができるか一緒に考えたい」と、受診の必要性を真摯に説明します。
それでも本人が拒否する場合、就業規則に基づき、限定的・例外的な措置として**「業務命令」としての受診命令**を検討します。
命令に従わない場合は、懲戒処分ではなく、まずは「安全配慮義務の観点からの就業禁止(自宅待機命令)」を検討するのが一般的です。その間の賃金の取り扱い(私傷病による休職規定に準じる等)も就業規則で定めておく必要があります。
受診命令の有効性に関する主な判例
電電公社帯広局事件(最判昭和61年3月13日)
就業規則や健康管理規程に基づき、健康回復を目的とした医師の受診命令について、合理性・相当性があれば労働者は従う義務があると判断されました。受診命令を拒否した場合の懲戒処分も有効とされました東京高裁昭和61年11月13日判決
就業規則に受診命令の規定がなくても、合理的かつ相当な理由があれば受診命令が認められると判断されています名古屋地裁平成18年1月18日判決
一方で、「精神科医の受診命令はプライバシー侵害の可能性が高い」とした裁判例も存在します
厚生労働省の通達・ガイドライン等
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
メンタルヘルス不調者への対応として、まずは本人の同意を得て受診を促すことが基本とされており、強制的な受診命令は慎重に運用すべきとされています
「受診は強制の形をとるのではなく、できる限り本人に治療への意思をもたせるような対応を心がける」と明記されています7。
ストレスチェック制度 実施マニュアル
高ストレス者への医師面接指導は、本人の申出を前提としており、強制ではありません
厚労省や関連団体のQ&A
メンタル不調が疑われる場合、まずは面談や受診勧奨を行い、就業規則等に受診命令規定があれば合理性・相当性の範囲で命令が可能とされています
受診命令の発令は「最後の手段」とし、本人とのコミュニケーションや自主的な受診を促す段階を踏むことが推奨されています
実務上のポイント
受診命令を出す際の注意点
- 就業規則等に根拠規定があることが望ましい。
- 客観的な事実(勤怠不良、業務ミス、異常言動等)がある場合に限り、合理性・相当性が認められる。
- プライバシー配慮や本人の納得を得る努力が重要。
- 受診命令の乱用は違法・無効と判断されるリスクがある。