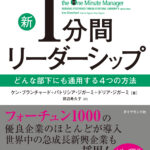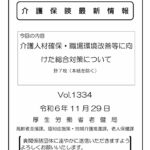小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(素案)が示されました|医療・介護・福祉の「小さな職場」に何が求められるのか
令和7年5月14日に公布された労働安全衛生法改正により、これまで「当分の間・努力義務」とされてきた労働者数50人未満の事業場でも、ストレスチェックの実施が義務化されることになりました。施行日は「公布の日から3年以内に政令で定める日」とされており、今後具体的な日付が決まっていく見込みです。
これを受けて、令和7年11月10日に開催された
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会
「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ 第4回
で、「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)」(素案)が資料として提示されました。
今回示されたマニュアル(素案)は、
- 労働者数50人未満の事業場
- なかでも単独型(1事業場がそのまま小規模)の事業場
を主なターゲットとしつつ、
- 商工会・協同組合などの業界団体所属型
- 商店街や工業団地などの地域集積型
- 大企業の営業所・チェーン店などの単独企業分散型の小規模拠点
にも参考にしてほしい、と位置づけられています。
医療法人のクリニック、特養1拠点だけの社会福祉法人、訪問介護事業所、就労支援事業所、そして中小企業の本社・営業所など――「常時使用労働者が50人未満」のほとんどの現場が、数年内にストレスチェック義務の対象になります。
【参考サイト】ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ 第4回資料
【参考資料】小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)
マニュアル(素案)のねらいと全体像
小規模事業場に合わせた「現実的で実効性のある」モデル
現行のストレスチェック実施マニュアルは、50人以上の事業場の体制を前提に作られています。産業医や衛生管理者がいて、総務人事部門があり…という想定です。
しかし、実際の医療・介護・福祉・中小企業の現場では、
- 産業医がいない
- 総務と人事と経理が同じ担当者
- そもそも「安全衛生」の専門担当がいない
といった状況が一般的です。
そこで今回の「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(素案)」では、
- 人員が限られていても回せる実施フロー
- 外部委託を前提にした実施体制
- 労働者のプライバシーを守るための具体的な工夫
を、小規模向けに落とし込んだ形で整理しています。
7つの論点で押さえる「素案」のポイント
マニュアル(素案)では、とくに次の7つの論点が重視されています。
ここからは、医療・介護・福祉・中小企業の現場をイメージしながら、実務的な意味合いを整理していきます。
1.関係労働者の意見を聴く機会の活用
「上から決めた」制度にしない工夫
マニュアルでは、ストレスチェック導入にあたって、関係労働者の意見を聴くことが明記されています。
具体的には、
- 事業者が導入方針をメッセージとして表明する
- 「社内ルールの案」をあらかじめ作り、事業場内に周知
- ミーティングや掲示、回覧などで現場から意見を募る
といったやり方が例示されています。
医療・介護の現場であれば、
- 各ユニットリーダー会議で案を共有
- 職員集会や部署ミーティングで意見を回収
- 夜勤者・パート職員にも周知の機会を確保
など、シフト勤務者をどう巻き込むかがポイントになります。
「形だけの意見聴取」にしないコツ
マニュアルが示すのは「意見を聴く機会の設置」ですが、実際には
- 「反対されないようにサラッと説明だけ」
- 「とりあえず全員にメール送ったのでOK」
となりがちです。
小規模職場の強みは、顔の見える関係があることです。
その強みを活かして、例えば
- 「制度の目的(メンタル不調の未然防止)」「結果の扱い」「プライバシー保護」を中心に説明する
- 「気になることは何でも書いてください」と匿名アンケートを併用する
といった工夫により、現場の不安や誤解を早い段階で拾うことが重要になります。
2. 事業者の関わり方と外部委託先の選定
小規模事業場では「外部委託」が原則
マニュアルは、労働者数50人未満の事業場では、原則として外部機関への委託が推奨されるとしています。
理由は明快で、
- 職員のプライバシーを守る
- 特に人事権を持つ管理者が個人結果を扱わないようにする
ことが重視されているからです。
外部機関としては、健診機関などが想定されていますが、どこでもよいわけではありません。マニュアルは「サービス内容事前説明書」を用いて、次の点を確認するよう求めています。
- 実施体制(実施者の資格、実施事務従事者)
- 調査票、実施方法、高ストレス者や面接指導対象者の選定方法
- 集団分析、相談窓口などのサービス範囲
- 情報管理体制(個人情報保護、データ保存の方法など)
料金の見方 ― 「何が基本で、何がオプションか」
マニュアルが特徴的なのは、料金体系への踏み込み方です。
ストレスチェック実施の受託料金について、
- 実施者・実施事務従事者の人件費
- 実施事務経費
- システム提供
- データ保管
といった実施に不可分な費用は、原則として基本料金に含まれるのが標準的と考えられる、と明記されています。
にもかかわらず、これらが「オプション(別料金)」扱いになっている場合は、料金設定について十分な説明を受けるべきだ、と注意喚起しています。
医療・介護法人では、ベンダーからの見積書が複雑になりがちです。
- 「一見安いが、実は“必須オプション”が多い」
- 「集団分析の費用が別途高額」
といったパターンを見抜くうえで、このマニュアルの視点は非常に実務的です。
「委託しても責任は事業者」という大原則
もう一つ重要なのは、
ストレスチェック制度は事業者の責任において実施するものである
と明示されている点です。
外部委託したとしても、
- 実務担当者を誰にするか
- どの範囲まで事業場内で把握するか
- 面接指導後の就業上の措置をどう決めるか
といった部分は、事業者が自ら考え、意思決定する必要がある、という姿勢が貫かれています。
3. 調査票(項目数、調査形態など)の選び方
推奨されるのは「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」
マニュナルは、ストレスチェックの調査票として、
- 職業性ストレス簡易調査票(57項目)
を利用することを推奨しています。簡略版の23項目版も紹介されていますが、集団分析の精度を考えると57項目版が基本になります。
紙か、Webか ― 現場の実情で選ぶ
調査形態としては、
- 紙の調査票
- Web上での回答
のいずれも認められていますが、マニュアルは「職場の実情に即して選ぶ」ことを強調しています。
特に、
- 1人1台のPCがない
- 個人の社用メールアドレスがない
- 私物スマホを業務に使うことを認めていない
といった職場では、紙での実施が適している場合もあるとされています。
高齢者施設や障害者支援施設では、現場職員にPCが支給されていないケースも多く、「Webの方が楽そうに見えて、実は回らない」という状況に陥りやすい部分です。
4. 面接指導 ― 情報提供の範囲と「地産保」の活用
医師に渡す情報は何か
高ストレス者から申出があった場合の医師による面接指導について、マニュアルは、医師に提供する情報として次のような項目を挙げています。
- 労働者の氏名・性別・年齢・所属・役職等
- 個人のストレスチェック結果(ストレスプロフィール)
- 直前1か月の労働時間・日数・深夜業の回数や時間・業務内容など
- 定期健診・その他の健診結果
- ストレスチェック実施時期が繁忙期であったかどうか
これらを事前に取りまとめて医師に提供することが望ましいとされています。
なお、ストレスチェック結果は、
- 委託先から密封封筒で取り寄せて医師に送る
- 本人に持参してもらう
など、事業場側が中身を見ない形で医師に渡す配慮が求められます。
地域産業保健センター(地産保)の無料活用
医師による面接指導について、小規模事業場では地域産業保健センター(地産保)を利用して無料で受けられることが明記されています。
ただし、
- 地産保はストレスチェック自体は実施しない
- ストレスチェックの実施者を地産保の医師に委託することもできない
といった整理も、あわせて示されています。
5. 集団分析と職場環境改善 ― 「10人」というライン
集団分析は「10人以上」が原則
マニュアルは、集団分析の単位が10人を下回る場合には、原則として集団分析の結果提供を受けてはいけないとしています。
これは、
- 結果から個人が特定されるおそれが高まる
- 「あの部署の結果は誰の影響か」が噂になる
といったリスクを避けるためです。
そのため、
- 10人未満の事業場
- 10人以上の事業場の中の、10人未満のユニット
では、原則として集団分析を行わないとされています。
集団分析の目的は「監視」ではなく「環境改善」
マニュアルでは、集団分析をもとにした職場環境改善の事例が複数紹介されています。例えば、
- 高温環境が負担と分かり、スポットクーラーや遮熱塗料、空調導入を行った事例
- 照度不足が課題で、工場内照明をLEDに変更した事例
- 言葉遣いが強い先輩に若手が萎縮している状況を踏まえ、ハラスメント防止研修を実施した事例
- 情報共有不足を背景に、ホワイトボード設置や情報交換会を行ったことで職場の一体感が高まった事例
いずれも、個人を責めるのではなく、職場環境や組織の運営方法を変える方向に舵を切っている点が共通しています。
医療・介護の現場でも、
- 夜勤負担の偏り
- 入浴介助や送迎など身体的負荷の集中
- 管理者のサポート不足
といった要因は、制度やシフトの組み方で軽減できることが少なくありません。
6. 労働者のプライバシー保護 ― 「要配慮個人情報」としての扱い
事業者が「知ってよい情報」はどこまでか
マニュアルは、ストレスチェック結果が個人情報保護法上の「要配慮個人情報」にあたることを明確にしたうえで、
- 事業者は、個人結果を不正に入手したり、提供を強要したりしてはならない
- 個人結果を事業者が提供を受ける必要がある場面は限られている
- 合理的理由と本人の事前同意があって提供を受ける場合でも、利用・共有は必要最小限にとどめる
といった原則を示しています。
医師の意見書にも「限度」がある
面接指導結果についても、
- 医師が事業者に提供できるのは、就業上の措置を検討するために必要最小限の情報に限られる
- 診断名・検査値・詳細な愁訴内容など、医学的な生データは事業者に提供してはならない
- 事業者側も、こうした情報提供を求めてはならない
と明記されています。
これは、医療・介護法人にとって非常に大事なポイントです。
同じ法人の中であっても、
- 医療職として診療に従事する立場
- 使用者として労務管理を行う立場
は、法的にも倫理的にも区別して考える必要があることを改めて示しています。
7. 10人未満など「特に小規模」な事業場での実施
実務担当者は誰が担うのか
労働者数10人未満の事業場では、衛生推進者・安全衛生推進者の選任義務がありません。マニュアルは、その場合、
事業者自らが、衛生推進者等に求められる役割を踏まえつつ、事業場内の実務を担うことが望まれる
と整理しています。
つまり、院長・施設長・社長自身が「実務担当者」として動く前提で制度設計を考える必要があります。
業界団体・商工会などでの共同実施
また、業界団体所属型・地域集積型の小規模事業場が、
- ストレスチェックの実施
- 集団分析
を共同で行う場合にも触れられています。
その際、
- 団体の事務局が結果を扱う場合も、プライバシー保護に十分留意する必要がある
- 10人未満の集団単位では、原則として集団分析を行わない
というルールは変わりません。
医療・介護・福祉・中小企業が「今から」準備しておきたいこと
ここからは、マニュアル(素案)の内容を踏まえつつ、当事務所として、現時点で取り組んでおくとよいと考えるポイントを整理します。
※以下は「法律でこう決まっている」という話ではなく、マニュアル(素案)の方向性に沿った実務上の提案です。
1.まずは「方針表明」と「社内ルール案」の叩き台づくり
- 「ストレスチェックを何のために導入するのか」
- 「結果は誰がどの範囲まで見るのか」
- 「面接指導や就業上の措置はどのような流れにするのか」
といった骨格を、事業者自身が最初に言語化することが大切です。
マニュアルの例文をベースに、
- 院長・施設長名で職員向けメッセージを作成
- 就業規則や安全衛生規程との整合を意識した「社内ルール案」を作る
といったステップを踏んでおけば、法令施行時の混乱をかなり抑えられます。
2.委託先候補を早めにリストアップし、「サービス内容事前説明書」を求める
- すでに健診を委託している医療機関
- 産業保健総合支援センターから紹介された機関
- 既にストレスチェックを実施している同業他社の利用先
などを参考に、候補となる外部機関を早めに洗い出しておくとよいでしょう。
そのうえで、マニュアルのフォーマットに沿った「サービス内容事前説明書」の提出を依頼し、
- 実施体制
- 調査票・実施方法
- 集団分析・相談窓口の有無
- 料金体系と基本/オプションの切り分け
- 情報管理(プライバシー保護)の仕組み
を比較検討していくことが現実的です。
3.労働時間・シフト・健康診断結果などの「基礎データ整備」
医師の面接指導では、
- 直前1か月の労働時間・休日労働・深夜業
- 担当業務の内容(責任の重さなど)
- 定期健診結果
といった情報をまとめて提供することが望ましいとされています。
これは裏を返すと、
日頃から労働時間やシフト、健診結果が整理されていないと、必要な情報をそろえられない
ということでもあります。
医療・介護現場では、
- 紙のタイムカードと別のシフト表
- 健診結果が紙バインダーにバラバラ
といった状況も少なくありません。ストレスチェック義務化を「データ整理を進めるきっかけ」にする視点も有効だと考えます。
4.「相談窓口」のメニューを見直す
マニュアルは、面接指導以外の相談窓口として、
- 厚生労働省の「こころの耳」(電話・SNS・メール相談等)
- 委託先外部機関が提供する相談サービス
- 自社のカウンセラーや相談窓口
などを案内することを推奨しています。
医療・介護法人の中には、
- EAP(従業員支援プログラム)
- 外部カウンセラーとの契約
を既にお持ちのケースもありますが、職員に十分認知されていないことも多い印象です。
ストレスチェック導入を機に、
- 相談窓口の一覧を整備
- 匿名性や利用条件をわかりやすく説明
することは、制度の信頼性を高めるうえで欠かせません。
メンタルヘルス対策を「人材定着の基盤」に変えていくために
マニュアル(素案)は、ストレスチェック制度の意義として、
- メンタルヘルス不調の未然防止
- 不調者発生時の長期病休による人材損失の回避
- 生産性向上・人材確保・定着・企業価値向上への寄与
といった点を挙げています。
医療・介護・福祉・中小企業の現場では、
- 1人休めば即シフトが回らなくなる
- 特定職員に負荷が集中しやすい
- 人材採用自体が難しい地域も多い
という現実があります。
このような環境では、メンタルヘルス不調者が1人出るだけで組織全体に大きな揺らぎが生じることは、日々の実感としてお持ちではないでしょうか。
ストレスチェック制度は、
- 管理職が部下のストレス状況に意識を向ける
- 現場の業務量やコミュニケーションの課題が「見える化」される
- 就業上の措置を通じて働き方の見直しが進む
という意味で、人材定着の土台づくりに直結し得る仕組みです。
当事務所としての見解|「数字」だけではなく、「働く人の声」と向き合う契機として
最後に、このマニュアル(素案)に対する当事務所の見解です。
小規模事業場だからこそ、「制度の設計」が決定的に重要
小規模な医療・介護・福祉事業所では、
- 「家族的な雰囲気」
- 「顔が見える安心感」
が強みである一方で、
- 噂がすぐに広がる
- 上司と部下の距離が近く、断りにくい
という側面もあります。
ストレスチェック結果が、
- 「あの人が高ストレスらしい」
- 「正直に書いたら評価に影響しそう」
といった形で扱われれば、制度への信頼は瞬時に失われます。
だからこそ、
- 個人結果は事業者が見ない
- 面接指導に進んだことを理由に不利益な取扱いはしない
- 集団分析は10人以上に限定し、個人が推測される運用はしない
といった原則を、就業規則や社内ルールのレベルで明文化し、日常のコミュニケーションの中で繰り返し確認することが重要だと考えます。
「チェックをやること」より、「結果をどう使うか」が問われる
制度が義務化されると、どうしても
とりあえず年1回、57項目のチェックをやればいい
という発想になりがちです。
しかし、マニュアルが繰り返し強調しているのは、
- 高ストレス者への面接指導や就業上の措置
- 集団分析を通じた職場環境の改善
までを含めた一体的な取り組みだということです。
言い換えれば、
- ストレスチェックは「警報装置」
- 面接指導と就業上の措置は「個別対応」
- 集団分析と職場環境改善は「構造的な改善」
という3つのレイヤーで考える必要があります。
当事務所としては、
- 就業規則・安全衛生規程との整合をとりながら、ストレスチェックの位置づけを明確にすること
- 集団分析の結果を、人事評価や人選の材料ではなく、業務設計・体制づくりの見直しに活かす発想を持つこと
が、医療・介護・福祉事業所の人材定着と経営安定に直結すると考えています。
「ストレスチェック」を入口に、働き方・組織文化を見直す
マニュアルの中には、
- 暑熱環境への対策としてスポットクーラーや遮熱塗装、空調を整備した事例
- ハラスメント防止研修やコミュニケーション改善の取り組み
- 情報共有の仕組みを整えたことで、職場の一体感が高まった事例
などが紹介されています。
これらは、単にメンタルヘルス対策という枠を超えて、
- 安全配慮義務の履行
- 業務効率化
- サービス品質の安定
にもつながる取り組みです。
医療・介護・福祉の現場では、
- 利用者・患者の命や生活を支えるプレッシャー
- 感情労働の蓄積
- 慢性的な人員不足
といった要因が重なり合っています。
ストレスチェック制度は、こうした負荷を「個人の問題」として片づけるのでなく、「職場としてどこを変えるべきか」を考えるための“問い”を投げかける仕組みとして活用されるべきだと考えます。
当事務所にできる支援について
当事務所では、ストレスチェックそのものの実施・運営は行っていませんが、
- ストレスチェック制度に関する社内ルール・就業規則・安全衛生規程の整備
- 外部委託先のサービス内容や契約条件のチェックと比較検討のサポート
- 面接指導後の就業上の措置、勤務区分・配置転換・休職制度などの労務面の設計・見直し
- 集団分析結果を踏まえた職場環境改善や人事制度との接続に関する助言
といった点での支援は可能です。
「義務化されたから仕方なくやるストレスチェック」ではなく、
- 職員が安心して働き続けられる
- 組織としても持続可能性が高まる
そんな仕組みとしてストレスチェック制度を活かしていきたい、と考えています。
小規模事業場向けマニュアルは、まだ素案の段階であり、今後の検討や最終版で表現が修正される可能性もあります。
しかし、その方向性――「小規模だからこそ、プライバシーを守りつつ、現実的に回るやり方を示す」というメッセージは、すでに十分に読み取ることができます。
・自事業所の規模や体制に、このマニュアル(素案)のどの部分がそのまま当てはまり、どこを工夫すべきか
・人材定着とサービス品質向上の観点から、ストレスチェックをどのように位置づけ直すか
一緒に考えていきたい経営者・人事担当の方は、ぜひ早い段階で当事務所にご相談いただければと思います。
【参考サイト】ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ 第4回資料
【参考資料】小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)