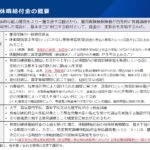「同一労働同一賃金」施行後5年見直し、論点案が出揃う!経営者が今、知るべきこととは?
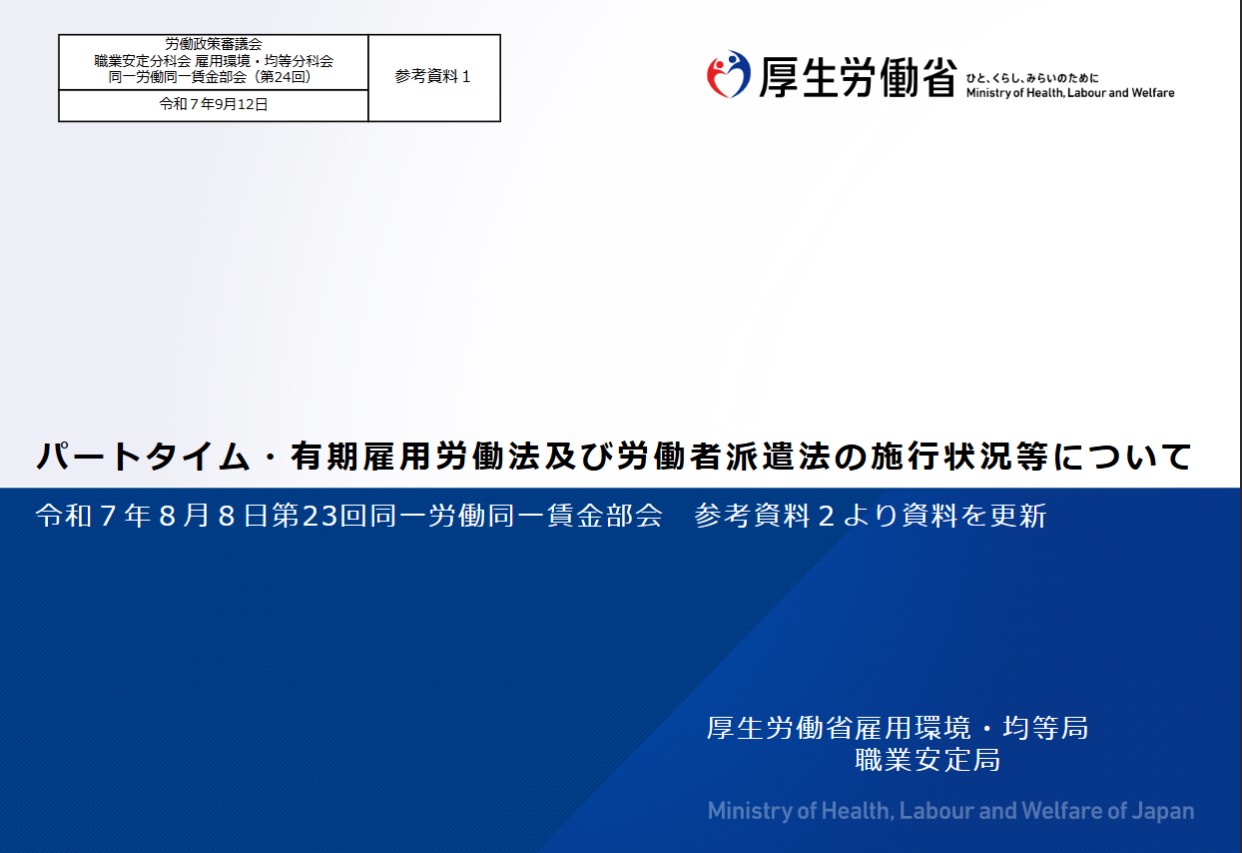 2025年9月12日開催の「第24回・同一労働同一賃金部会」で、施行後5年見直しに向けた論点(案)がまとまり、公表資料には、正社員転換・多様な正社員・キャリアアップの3領域を柱とする整理が明確に示されました。掲示ページには、これまでの主な意見の整理(資料1-1)、有識者・労使ヒアリングの概要(資料1-2・1-3)、正社員転換支援などの論点(案)(資料2)、そして詳細な統計・施行状況の更新版(参考資料1ほか)が公開されています。
2025年9月12日開催の「第24回・同一労働同一賃金部会」で、施行後5年見直しに向けた論点(案)がまとまり、公表資料には、正社員転換・多様な正社員・キャリアアップの3領域を柱とする整理が明確に示されました。掲示ページには、これまでの主な意見の整理(資料1-1)、有識者・労使ヒアリングの概要(資料1-2・1-3)、正社員転換支援などの論点(案)(資料2)、そして詳細な統計・施行状況の更新版(参考資料1ほか)が公開されています。
前回までの議論を踏まえ、裁判例や政府決定文書の最新反映も進んでいます。
医療・介護・障害福祉の職場にとっては、制度の“名称”よりも、日々の運用と説明可能性を底上げする局面に入った、と読むのが妥当です。
【参考サイト】第24回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会
部会論点(案)の骨子:3つの柱を実務に引き直す
正社員転換――「掲げる」から「動かす」へ
資料では、非正規から正規への転換を実効化する観点から、本人意向の把握・情報公開・運用手順の明確化が問われています。現場レベルでは、転換ルート(応募資格、評価基準、判断時期、窓口)を就業規則・社内ポータル・求人票で同じ言葉で示し、年に複数回の意向確認を面談に組み込むといった“導線の可視化”が鍵になります。特にシフト運用が複雑な医療・介護では、「同種同等業務」の範囲や責任密度を職種定義書で明文化し、比較可能性を確保しておくことが、のちの説明義務の質を大きく左右します。
実務の勘所
夜勤・オンコール・感染対応など、負担配分の差異が待遇差に反映される構図を、職務定義と評価軸に一体で落とし込むこと。転換時に“フル常勤一択”にせず、受け皿として短時間・地域・職務限定などの区分をあらかじめ設計しておくと、離職抑止と人員充足に同時に効きます。
「多様な正社員」の普及――受け皿の設計力
論点(案)は、短時間正社員をはじめとする限定型の正社員を、転換の受け皿として普及させる方向性を明示しました。2025年度には、働き方改革推進支援センターにおけるコンサルティング実施も付記されています。医療・介護では「時間帯限定×職務限定」の設計が親和的で、評価項目・手当の趣旨・昇給ロジックを限定要件に合わせて再定義すると、説明の一貫性が保ちやすくなります。
厚生労働省
実務の勘所
“同じ正社員でも区分が違えば評価軸も違う”という前提を明文化し、賃金テーブルや賞与配点表、異動のルールまで連動させること。制度の名前だけ変えても、運用の筋道と帳票が伴わなければ定着しません。
厚生労働省
キャリアアップ――訓練と賃金決定の“接続”
非正規の能力開発を底上げする観点から、企業内訓練(OJT/Off-JT)を台帳化し、賃金・昇格・職務拡大と論理的に接続することが示されています。医療・介護の多職種チームでは、技能マップ(コンピテンシー)を職種ごとに作り、次の等級・昇給への到達要件を明確にしておくと、説明義務対応の「土台書類」にもなります。
厚生労働省
実務の勘所
「誰が・何を・どの水準までできるか」を見える化し、受講・修了・評価の記録を整備。昇給や手当の変更理由を、台帳・評価表・賃金決定の三点で整合させる――この“接続”が最短のリスク低減策です。
具体的な論点(案)を徹底解説!何がどう変わるのか?
今回出揃った論点(案)は、多岐にわたります。ここでは特に経営者の皆様に関わりの深いポイントを、三つのカテゴリーに分けて解説します。
より厳格に、より明確に。パート・有期、派遣法の見直し
パートタイム・有期雇用労働法と労働者派遣法については、共通して以下の点が論点として挙げられています。これは、現行法の実効性をさらに高めようという国の強い意志の表れです。
・均等・均衡待遇の徹底:待遇差が不合理か否かの判断を、より厳格に行うための見直し。
・待遇に関する説明義務の強化:労働者から求められた際の、待遇差に関する説明内容や方法をより具体的に。
・公正な評価の推進:賃金だけでなく、能力評価やキャリアアップの機会についても公正性を確保する仕組み。
・意見聴取の機会の確保:非正規雇用労働者が、待遇改善などについて意見を表明しやすくなるような措置。
・情報公表の促進:企業の取り組み状況を外部から見えるようにし、自主的な改善を促す。
・行政による履行確保:行政指導や助言の実効性を高める方策。
これらの項目は、これまで以上に「なぜ正社員と待遇が違うのか?」という問いに対し、企業が客観的かつ合理的な説明責任を負うことになる可能性を示唆しています。
実務上の判断基準が変わる!「ガイドライン」の見直し
実務上、最も影響が大きいのが、このガイドラインの見直しでしょう。特に注目すべきは以下の点です。
最新の裁判例の反映:近年、同一労働同一賃金を巡る最高裁判決が相次ぎました。賞与や退職金、各種手当について示された司法の判断をガイドラインに盛り込むことが検討されています。特に、これまで記載のなかった「住宅手当」や「扶養手当」など、高裁レベルで判断が示された手当の扱いが明記される可能性があります。
「正社員人材確保論」の追加:正社員の離職を防ぎ、長く定着してもらうために待遇を手厚くするという企業の主張(いわゆる正社員人材確保論)について、一定の考慮要素としてガイドラインに記載されるかが焦点です。ただし、これが安易な待遇差の理由として使われないよう、慎重な検討が求められます。
「その他の事情」の明確化:待遇差の合理性を判断する際の「その他の事情」について、より具体的な例示が追加され、判断基準が明確化される見込みです。
「多様な正社員」等への考え方の波及:勤務地限定正社員や短時間正社員など、いわゆる「多様な正社員」や、契約期間は無いもののフルタイムで働く労働者と、通常の正社員との間の不合理な待遇差解消についても、ガイドラインの考え方を及ぼしていく方向性が示されました。
ガイドラインの見直しは、貴社が現在支給している諸手当の妥当性を、根本から見直すきっかけとなり得ます。
単なる「格差是正」から「キャリアアップ支援」へ
今回の議論で特徴的なのは、単に賃金格差を是正するだけでなく、非正規雇用労働者のキャリア形成を積極的に支援する視点が強く打ち出されている点です。
・正社員転換支援の強化:希望する労働者が円滑に正社員へと転換できるような、企業の取り組みを後押しする施策。
・「多様な正社員」制度の普及促進:育児や介護と両立しながら働き続けられるなど、個々の事情に応じた多様な働き方を整備することの推奨。
・キャリアアップの促進:非正規雇用という理由で研修機会などが限定されることのないよう、能力開発の機会を均等に提供することの重要性。
これは、人手不足が深刻化する日本社会において、すべての労働者を貴重な人材として育成し、最大限に活用していくという国の方針転換を意味しています。
当事務所の見解|これは「コスト」ではなく、「未来への投資」である
さて、ここまで今回の論点(案)の概要を解説してきました。
多くの経営者様は、「また規制が強化されるのか」「人件費がさらに増大する」といった懸念を抱かれたかもしれません。もちろん、法改正への対応は不可欠であり、それに伴うコスト管理も重要です。
しかし、当事務所は、この一連の動きを、単なる「法規制の強化」という側面だけで捉えるべきではない、と考えています。
今回の見直しの根底に流れているのは、「人材の価値を、雇用形態という“ラベル”で判断する時代の終わり」という、極めて本質的なメッセージです。
これからの企業経営において、最も重要な資源は「人」です。特に、専門性が求められる医療・介護・福祉の現場では、職員一人ひとりのスキルと経験、そして仕事へのエンゲージメントが、サービスの質、ひいては事業所の評判や収益に直結します。
そのような状況で、「パートだから」「有期契約だから」という理由だけで、職務内容や貢献度が同じであるにも関わらず、待遇に大きな差を設け続けることは、もはや経営上のリスクでしかありません。優秀な人材はより公正な評価をしてくれる職場へと流出し、残った職員のモチベーションは低下するでしょう。結果として、サービスの質が落ち、人材獲得コストは増大し続けるという悪循環に陥りかねません。
今回の見直しは、そうした旧来の人事管理からの脱却を、社会全体で促すものです。
これは、貴社の人事制度を、「人を管理するためのルール」から、「人が育ち、定着するためのプラットフォーム」へと進化させる、またとない機会だと思います。
職務内容や貢献度、能力を正当に評価し、それに見合った待遇を決定する。雇用形態に関わらず、キャリアアップの道筋を示す。そうした「納得感」のある人事制度を構築すること。それこそが、これからの時代を勝ち抜くための、最も確実で効果的な「投資」ではないでしょうか。
この転換は、一朝一夕に成し遂げられるものではありません。職務分析・職務評価(ジョブ・ディスクリプションの整備)から始まり、賃金テーブルの再設計、評価制度の刷新、そして丁寧な従業員への説明と、やるべきことは山積しています。
当事務所は、社会保険労務士として、そして皆様と同じ中小企業の経営者として、その挑戦に寄り添います。法的なリスクを回避する「守りの労務管理」はもちろんのこと、今回の変革を好機と捉え、貴社の持続的な成長を支える「攻めの人事戦略」の構築を、全力でサポートさせていただきます。
まず何から手をつければ良いのか、自社の現状はどうなのか。どんな些細なことでも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。