令和8年施行へ!女性活躍・ハラスメント対策強化で企業に求められる次の一手とは?
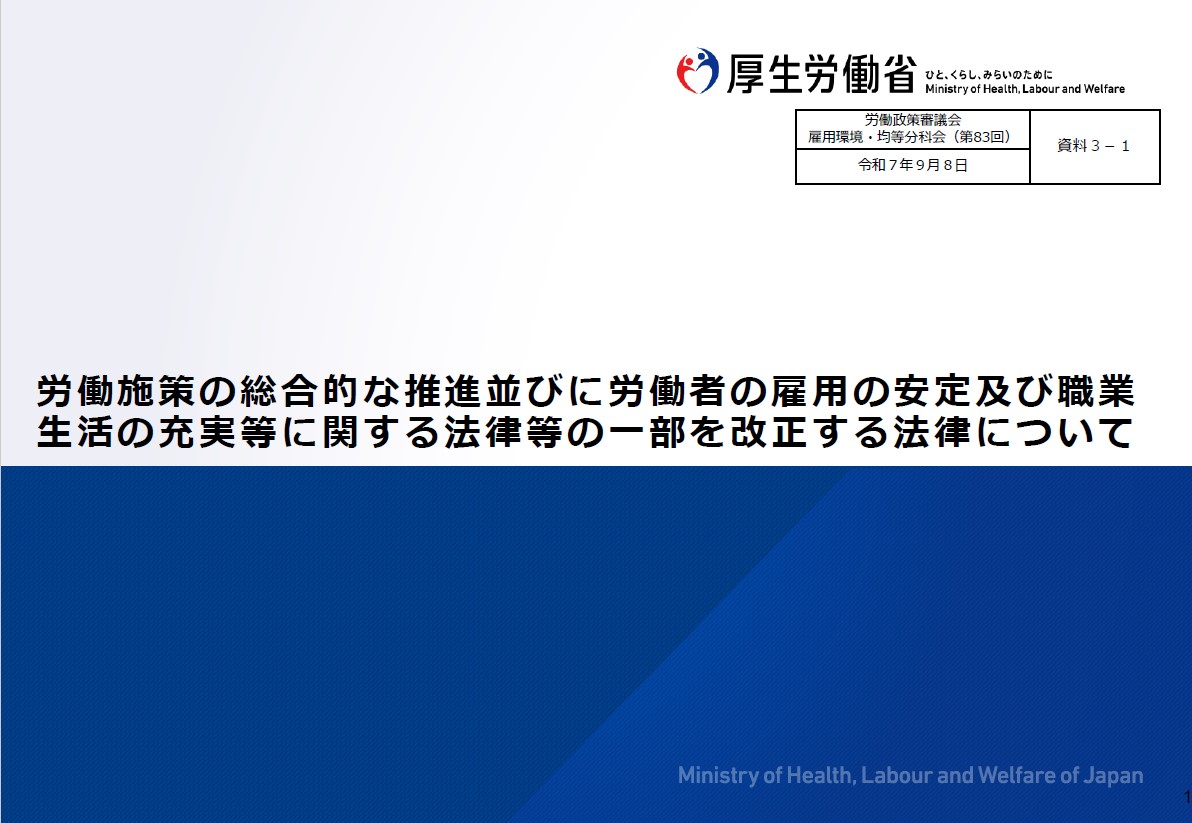 企業の労務管理において、また新たな対応が求められる時代が到来します。去る令和7年9月8日に開催された第83回労働政策審議会 雇用環境・均等分科会において、多くの事業主様、特に中小企業や介護・福祉事業所の経営者様にとって極めて重要な法改正の今後の姿が示されました 。
企業の労務管理において、また新たな対応が求められる時代が到来します。去る令和7年9月8日に開催された第83回労働政策審議会 雇用環境・均等分科会において、多くの事業主様、特に中小企業や介護・福祉事業所の経営者様にとって極めて重要な法改正の今後の姿が示されました 。
それは、「改正女性活躍推進法」と「改正労働施策総合推進法(ハラスメント対策関連)」の施行に向けた具体的なスケジュールです。
人手不足が深刻化し、多様な人材の確保・定着が経営の最重要課題となる現代において、これらの法改正は単なる「守りのコンプライアンス」ではありません。むしろ、来るべき変化の波を捉え、従業員にとってより魅力的な職場環境を構築し、持続的な成長を遂げるための「攻めの経営戦略」の核となり得るものです。
本稿では、示された最新情報に基づき、両改正法のポイントと、企業が今から何を準備すべきかを分かりやすく解説します。
【参考リンク】第83回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
【参考資料】第83回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 【資料3-1】労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律について
【参考資料】同上 【資料3-2】改正法施行に係る今後の検討スケジュール(案)
【参考資料】同上 【資料3-3】改正女性活躍推進法の施行に向けた主な検討事項
令和8年4月1日施行!「改正女性活躍推進法」の4つの柱
まず、多くの企業に影響を与える「改正女性活躍推進法」について、その施行スケジュールと具体的な検討事項を見ていきましょう。審議会では以下のスケジュール(案)が示されました 。
令和7年9月:改正女性活躍推進法関係の検討
~令和8年1月:改正女性活躍推進法関係の諮問
令和8年4月1日:改正女性活躍推進法関係の施行
令和8年4月の施行に向けて、主に以下の4つのテーマで検討が進められます。
情報公表義務の拡大:男女間賃金差異と女性管理職比率
今回の改正で最も注目される点の一つが、情報公表義務の対象拡大です 。これまで努力義務に留まっていた常時雇用する労働者数が101人以上の事業主に対して、以下の情報公表が義務付けられます 。
男女間の賃金差異
女性管理職比率
重要なのは、単に数字を公表して終わりではないという点です。男女間賃金差異については、その大小だけでなく、要因を分析し、課題を把握した上で改善に取り組むプロセスが重視されます 。そのために、企業の自主的な説明を記載できる「説明欄」の活用を促すことが検討されています 。
また、女性管理職比率についても新たに「説明欄」が設けられ、企業が定義する役職名を明記するなど、実態に即した的確な情報開示が求められる方向です 。
「女性の活躍推進企業データベース」の活用がカギに
情報公表の実効性を高めるため、国が運営する「女性の活躍推進企業データベース」の活用強化が打ち出されました 。常時雇用する労働者の数が101人以上の企業は、このデータベースを利用して情報公表を行うことが「最も適切である」と示される予定です 。
求職者が企業の取り組みを比較検討しやすくなることで、女性活躍に積極的な企業が選ばれやすくなる環境が整備されます。まさに、情報開示が採用力に直結する時代と言えるでしょう。
新たな視点:「職場における女性の健康支援」の推進
今回の改正では、女性活躍推進の基本原則に「女性の健康上の特性に配慮する」旨が明記されました
具体的には、以下のような取組例が示される予定です 。
職場におけるヘルスリテラシー向上のための取組
休暇制度の充実
女性の健康課題を相談しやすい体制づくり
性別を問わず利用しやすい特別休暇制度など、全従業員を対象とした取り組みも有効であるとされています 。
「えるぼし認定制度」の見直しとインセンティブ強化
女性活躍推進に関する取り組みが優良な企業を認定する「えるぼし認定」制度も、より多くの企業が活用しやすくなるよう見直されます 。具体的には、認定のハードルとなっていた要件が見直され、これまで認定取得を諦めていた企業にも門戸が広がる可能性があります 。さらに、新たな認定制度として「えるぼしプラス(仮称)」の創設が検討されています 。これは、職場における女性の健康支援に積極的に取り組む企業を評価するもので、企業のインセンティブを高める狙いがあります 。
カスタマーハラスメント対策が本格始動!「改正労働施策総合推進法」の行方
もう一つの大きな柱が、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策などを盛り込んだ「改正労働施策総合推進法」です。こちらのスケジュール(案)は以下の通りです 。
令和7年9月~令和8年1月:ハラスメント対策関係の検討(消費者・障害当事者団体ヒアリングを含む)
令和8年1月~令和8年4月1日:ハラスメント対策関係の諮問
改正法の公布の日(令和7年6月11日)から起算して1年6ヶ月以内で政令で定める日:ハラスメント対策関係の施行
この改正により、事業主には顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)を防止するため、雇用管理上の必要な措置を講じることが義務付けられます 。
現時点で詳細な検討事項は示されていませんが、国会での法案審議の際に採択された「附帯決議」に、今後の指針(ガイドライン)策定の方向性を示す重要な記述が多数含まれています。
現場の声を反映へ:実効性ある指針策定に向けた動き
附帯決議では、現場で実際に機能する実効性のある対策が求められており、今後の指針には以下のような内容が盛り込まれるよう検討が進むと考えられます。
実効性のあるカスタマーハラスメント対策
労働者が相談した際に、形式的でなく実効性のある対応が行われるような指針を策定すること 。
警察との連携や仮処分命令の申立てといった、具体的な抑止措置を指針に示すこと 。
SNS等で無断で撮影された顔写真や名札が拡散されるといった誹謗中傷が、カスタマーハラスメントに該当し得ることを指針に明記するよう検討すること
30 。
SOGI(性的指向・性自認)に関するハラスメント
本人の意に反してSOGIを暴露する(アウティング)などの行為がパワーハラスメントに該当し得ることや、顧客等からのSOGI関連のハラスメントがカスタマーハラスメントに該当し得ることを、関連指針に明記し周知啓発を行うこと 。
治療と仕事の両立支援
事業主に努力義務が課される「治療と仕事の両立支援」についても、守秘義務に留意した上で、産業医と主治医の効果的な情報交換のあり方や、職場復帰に向けた相談窓口の明確化などを検討すること。
これらの内容は、特に介護・福祉施設や医療機関など、対人サービスを主とする事業所にとって、従業員を守り、サービスの質を維持するために極めて重要な視点となります。
当事務所の見解|法改正を「リスク」から「成長の好機」へ転換するために
ここまで最新の動向を見てきましたが、これらの法改正を前に、経営者や人事担当者の皆様は何を感じられたでしょうか。「また義務が増えるのか」「対応が大変だ」といった懸念が先に立つかもしれません。しかし、当事務所は、この変化を異なる角度から捉えるべきだと考えています。
人材獲得競争を勝ち抜くための「選ばれる職場」づくり
人手不足が常態化している日本において、特に専門性が求められる介護・福祉・医療の現場では、人材はまさに「宝」です。今回の法改正は、その宝である人材から「選ばれる職場」とは何かを具体的に示してくれています。
女性従業員が多数を占めるこれらの業界において、「女性活躍推進」は単なるスローガンではありません。
男女間の賃金差異を分析し、その背景にある評価制度やキャリアパスを見直すことは、働く意欲と納得感を高め、優秀な人材の定着に直結します。女性の健康支援に取り組む姿勢は、従業員を大切にする企業文化の証となり、求職者に対する強力なメッセージとなります。「えるぼし認定」などの外部認証は、そのメッセージを客観的に証明する切り札となり得るでしょう。
サービスの質を守り、職員を守る「健全な職場環境」の構築
対人サービスの最前線では、利用者様やそのご家族との信頼関係がサービスの根幹を成します。しかし、その関係性が時に従業員への過度な負担となり、カスタマーハラスメントという形で現れることも少なくありません。
従業員が心身の安全を脅かされることなく、安心して働ける環境を整備することは、経営者の責務です。明確なハラスメント対策方針を掲げ、相談窓口を機能させ、いざという時には組織として従業員を守る姿勢を示すこと。これは、従業員の精神的な安定を守り、結果として提供するケアやサービスの質の維持・向上につながります。従業員の疲弊による離職を防ぎ、安定したサービス提供体制を維持することは、事業の継続性そのものを支える経営基盤の強化に他なりません。
今、経営者が取り組むべきこと
施行はまだ先ですが、準備を始めるのに早すぎるということはありません。むしろ、法の施行を待ってから動くのでは後手に回ってしまいます。
今から着手すべきは、自社の「現在地」の正確な把握です。
男女別の賃金データや管理職登用状況を整理・分析できていますか?
ハラスメントに関する社内規程は、最新の法改正の趣旨を反映したものになっていますか?
従業員が心身の不調や悩みを気軽に相談できる窓口はありますか?
これらの問いに即答できないのであれば、今がまさに変革の好機です。
法改正への対応は、就業規則や関連規程の改定、新たな制度設計、管理職や従業員への研修など、専門的な知識と計画的な実行が求められます。
当事務所は、労働法務の専門家として、これらの法改正への実務的な対応はもちろんのこと、その先にある貴社の持続的な成長を見据えた組織づくりをサポートします。法改正という変化の波を、貴社が力強く乗りこなし、より良い未来へと漕ぎ出すための羅針盤となること。それが当事務所の使命だと考えています。
企業の数だけ、課題の形は異なります。まずは貴社の現状をお聞かせください。未来に向けた組織づくりの第一歩を、ご一緒に踏み出せれば幸いです。
【参考リンク】第83回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
【参考資料】第83回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 【資料3-1】労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律について
【参考資料】同上 【資料3-2】改正法施行に係る今後の検討スケジュール(案)
【参考資料】同上 【資料3-3】改正女性活躍推進法の施行に向けた主な検討事項









