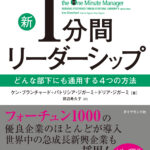『身元保証人がいません』その一言に、どう向き合いますか?
都内の総合病院で入院中だったTさん(73歳・男性)は、治療が無事に終わったにもかかわらず、保証人がいないことを理由に退院できない状態が続いていました。独居で身寄りがなく、頼れる親族もいない状況。施設入所を勧められても、「保証人がいないなら入所はできません」と断られる日々。
そんななか、病院の医療ソーシャルワーカーが紹介したのが「身元保証サービス」でした。契約を結んだことで、無事に特別養護老人ホームへ入所が決まりました。Tさんのケースは、「誰かが保証してくれなければ次の生活に進めない」―――そんな現実を浮き彫りにしています。
このような例は決して珍しくありません。65歳以上の一人暮らし世帯が約700万世帯に迫り(2020年国勢調査 )、2040年には身元保証人を立てることが難しい高齢者が1,000万人を超えるとも予測される現代。この「身元保証人がいない」という問題は、もはや一部の特殊なケースではありません。
当事務所では、日々、多くの法人様から労務管理のご相談を承る中で、この問題が職員の皆様の心身に大きな負担をかけ、ひいては組織運営そのものを揺るがしかねない重要な経営課題であると痛感しています。
本コラムでは、社会福祉法人や医療機関の経営者、管理職の皆様が、この避けては通れない課題と向き合うための一助として、「身元保証サービス」の現状と未来について、専門的かつ人間的な視点から、深く掘り下げてまいります。
なぜ今、「身元保証」がこれほどまでに注目されるのか?
かつて、家族や親族が当たり前に担っていた「身元保証」という役割。しかし、社会構造の変化が、その当たり前を過去のものにしようとしています。
加速する「おひとりさま社会」という現実
ご存知の通り、日本は急速な勢いで高齢化と核家族化が進んでいます。 内閣府の令和5年版高齢社会白書によれば、65歳以上の者がいる主世帯のうち、「単独世帯」と「夫婦のみの世帯」を合わせた割合は、1980年には約3割でしたが、2021年には6割を超えました。頼れる親族が遠方に住んでいたり、そもそも身寄りがなかったりする方が増え続けるのは、必然の流れと言えるでしょう。
この流れを受け、私たちのもとにも「入所希望者に身元保証人がいない場合、どこまで支援すべきか」「万が一の際の責任の所在が曖昧で、現場が疲弊している」といった切実な声が寄せられています。
急成長する市場が示す「ニーズの証明」
この社会的な“空白”を埋めるかのように、身元保証サービスの市場は驚くべきスピードで拡大しています。
株式会社矢野経済研究所の調査によれば、身元保証と生前整理を合わせた「終活関連ビジネス市場」は、2024年度に234.5億円に達し、2026年度には280.0億円規模まで成長すると予測されています[ 株式会社矢野経済研究所「終活関連ビジネスに関する調査(2025年)」]。年率約10%という驚異的な成長率です。
また、サービスを提供する事業者数も、2020年頃の約150社から、2022年には412事業者へと、わずか2年で2.7倍以上に急増しているというデータもあります[ 総務省「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査結果報告書」]。
これらの数字は、単なる一過性のブームではなく、社会全体の関心の高まりを物語っています。皆様のような施設・医療機関にとっても、この問題がいかに身近で重要な課題となっているかを示していると言えるでしょう。
解決の鍵「身元保証サービス」とは何か?
では、具体的に「身元保証サービス」とは、どのような役割を担ってくれるのでしょうか。 これは、家族や親族に代わって、法人格を持つ事業者が以下のような多岐にわたる支援を提供するサービスです。
身元保証・身元引受: 病院への入院時や介護施設への入所時に必要となる身元保証人・身元引受人になります。
緊急時の対応: 急な体調変化や災害時などに、ご本人に代わって連絡を受け、駆けつけなどの対応を行います。
生活事務のサポート: 日常的な金銭管理や役所での手続き、買い物代行など、生活上のこまごまとした事務作業を支援します。
医療に関する意思決定支援: ご本人の意思を尊重し、医療行為に関する同意の場面で支援を行います(※直接的な医療同意は法律上できませんが、本人の意思を伝える重要な役割を担います)。
死後事務委任: ご逝去後の葬儀や納骨、遺品整理、行政への届け出、各種契約の解約手続きなど、ご家族が行うべきだった死後の手続き一切を代行します。
これらのサービスは、ご本人の尊厳を守り、穏やかな晩年を支えるだけでなく、受け入れ側である施設や医療機関の皆様の業務負担や精神的なプレッシャーを大幅に軽減する可能性を秘めています。
国も動き出した~「ガイドライン」が示す新たな秩序
事業者が急増する一方で、残念ながら一部の悪質な業者による高額請求や契約トラブルが社会問題化したことも事実です。国民生活センターへの相談件数は年々増加傾向にあり、2023年度には家族代行サービス関連の相談が355件に上ったという報告もあります[日本経済新聞 2025年1月8日]。
こうした状況を受け、国もようやく重い腰を上げました。
2024年6月、歴史的な一歩「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」
2024年6月11日、厚生労働省は「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定・公表しました[ 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1273」]。これは、業界の健全な発展と消費者保護を両立させるための、国として初めての公式な指針です。
このガイドラインのポイントは、単なる規制強化ではありません。むしろ、この事業の社会的必要性を国が正式に認め、事業者が守るべきルールを明確にすることで、利用者が安心してサービスを選べる環境を整え、業界全体の健全な成長を後押ししようという明確な意思が示されています。
ガイドラインでは、契約内容の明確化、財産の保全措置、情報開示の在り方などが具体的に示されました。これは、皆様が提携する身元保証サービス事業者を選ぶ際の、信頼性を測るための「ものさし」となると言えるでしょう。
医療・介護現場へのメッセージ
また、国は以前から、医療機関や介護施設に対し、「身元保証人がいないことのみを理由に入院や入所を拒んではならない」という見解を示しています。これは、医師法における応召義務や、介護保険法における提供拒否の禁止の観点からも重要な指針です。
しかし、現場の実情としては、緊急連絡先の確保や残置物処理の問題など、身元保証人がいないことで生じるリスクを無視できないのも事実でしょう。
だからこそ、国が認める基準を満たした、信頼できる身元保証サービス事業者との連携が、法令遵守と安定した施設運営を両立させるための、現実的かつ最も有効な解決策となりつつあるのではないでしょうか。
【実践編】医療・介護現場で、どう向き合うべきか
ここまで、身元保証サービスの社会背景と国の動向を見てきました。では、日々、利用者様や患者様と向き合う皆様の現場では、このサービスをどのように捉え、活用していけばよいのでしょうか。
「保証」がもたらす、現場の安心と質の向上
想像してみてください。 緊急時、深夜でも必ず連絡がつき、的確な情報共有ができるパートナーがいる安心感。 入院費や施設利用料の支払いが滞るリスクが低減されることによる、経営の安定。 そして何より、ご逝去後の煩雑な手続きや残置物の問題から、現場の職員が解放されることの価値を。
身元保証サービスは、これらの課題を解決することで、職員の皆様が本来の専門業務であるケアや看護に集中できる環境を生み出します。それは結果として、サービスの質の向上、利用者満足度の向上、そして職員の離職率低下にも繋がる、非常に重要な投資と言えるのではないでしょうか。
ある介護サービス事業者は、身元保証サービスを組み合わせることで、売上を30%増加させ、同時に顧客満足度も向上させたという事例もあります。これは、利用者の「困りごと」にワンストップで応える体制が、結果的に法人の価値を高めることを示しています。
信頼できるパートナーの見極め方
しかし、前述の通り、事業者は玉石混交です。大切な利用者様・患者様を紹介するにあたり、パートナー選びは絶対に失敗できません。例えば、以下の点を、ぜひ厳しい目でチェックする必要があると思います。
- ガイドラインへの準拠: 厚労省のガイドラインを遵守する意思を明確に表明しているか。
- 契約内容の透明性: 料金体系は明瞭か。追加料金の発生条件など、不利な情報もきちんと説明されているか。
- 財産の保全措置: 利用者から預かる預託金などの財産は、信託銀行などを利用し、事業者の資産とは明確に分別管理されているか。これは倒産リスクに備える上で絶対条件です。
- 実績と体制: これまでの支援実績は十分か。緊急時に迅速に対応できるだけの人的・物理的な体制が整っているか。
- 理念と哲学: 何よりも、その事業者がどのような思いでこの事業に取り組んでいるか。単なるビジネスとしてではなく、人の尊厳を守るという高い倫理観を持っているか。
この課題は、もはや一施設、一病院だけの問題ではありません。地域包括ケアシステムが推進される中で、地域の社会福祉法人、医療機関、さらには信頼できる民間サービスが連携し、一体となって高齢者の暮らしを支える「チーム」を構築していくことが求められているのではないでしょうか。
身元保証サービスは、その「チーム」の、非常に心強い一員となり得る存在です。
この大きな変化の波を、単なるリスクとして捉えるのではなく、より良いケア、より良い地域社会を創造するためのチャンスとして捉える。そんな前向きな視点を持つことが、これからの経営者には不可欠なのかもしれません。
誰もが、年を取り、家族を持たず、誰にも頼れない状況になる可能性があります。そうなったとき、自分らしく生き、自分らしく死ぬことができるかどうか―――。
身元保証サービスは、その問いに対するひとつの“現代的な解”かもしれません。
しかし、サービスの広がりが進む一方で、その契約のあり方や、支える体制の在り方は、まだまだ模索の途上にあります。
本記事では、現在のサービスの実態と、政府の見解、市場動向などを紹介しました。最終的にこのサービスをどう活用すべきか、あるいはどう制度として整えていくべきかは、皆様自身が考え、選ぶべきテーマです。
当事務所でも、私たちの社会が、誰にとっても「安心して老いられる場所」となるよう、引き続き注視してまいります。