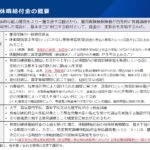地域医療構想は「在宅・介護連携」の新時代へ|2040年を見据えた国の最新動向
厚生労働省は去る7月4日、社会保障審議会医療部会に対し、2040年頃を見据えた医療・介護提供体制の具体的な検討を進めるための新たな体制案を提示しました
中核となる検討会と4つの専門的なワーキンググループ(WG)が設置され、今後の日本の医療・介護の姿を具体化する議論が本格的に開始されます。
本コラムは、社会福祉法人や医療機関の経営を担う皆様に向けて、この国の大きな舵取り、すなわち「新しい地域医療構想」の全体像と、その核心となる考え方を、解説いたします。
【参考サイト】第116回社会保障審議会医療部会
【参考資料】第116回社会保障審議会医療部会 資料1 地域医療構想、医師偏在対策等の検討体制について
なぜ今、大転換が必要なのか?|「治す医療」から「治し、支える医療」へ
今回の見直しの背景には、避けることのできない二つの大きな潮流があります。高齢化に伴う医療ニーズの「質」の変化と、人口減少による医療・介護人材の「量」の制約です
これまでの医療は、病気を治す「治す医療」が中心でした。しかし、多くの高齢者が複数の疾患(マルチモビディティ)を抱えながら生活する時代にあっては、単に病院で治療して終わり、というモデルは限界を迎えています。これからの地域医療は、治療はもちろんのこと、退院後の生活までを見据え、住み慣れた地域でその人らしい暮らしを継続できるよう支える**「治し、支える医療」**へと、その役割を明確にシフトすることが求められています
この理念の転換が、従来の「病床(ベッド)の再編」を主目的とした地域医療構想から、外来・在宅医療、そして介護との連携までを一体的に捉える、全く新しい構想へと舵を切る根本的な理由なのです
新しい地域医療構想の全体像と「在宅シフト」という核心
厚生労働省は、この大きな変革を実現するため、2024年(令和6年)から「新たな地域医療構想等に関する検討会」を重ね、その具体的な方向性を示しています
未来へのスケジュール
今後の大まかなスケジュールは以下の通りです。
- 2025年度(令和7年度): 国が新たな地域医療構想の「ガイドライン」を策定
。 - 2026年度(令和8年度): 各都道府県が、ガイドラインに基づき、地域の医療提供体制の将来像や必要病床数の推計に着手
。 - 2027年度~2028年度(令和9~10年度): 医療機関ごとの機能分化・連携の具体的な協議を開始
。
【構想の要】「在宅医療・介護連携」が示す未来
この構想の詳細を詰める4つのワーキンググループの中でも、今回の構想の「要」と位置づけられているのが「在宅医療・介護連携」です
特に、人口の少ない地域ではすでにその傾向が顕著であり、病院だけでなく診療所や、場合によっては病院自らが在宅医療の一定の役割を担っている実態もあります
国が示す「在宅医療の体制構築に係る指針」では、地域で確保すべき機能として、以下の4つが挙げられています
- 退院支援: 入院医療機関と在宅医療を担う機関がスムーズに協働し、患者の退院を支える
。 - 日常の療養支援: 多職種が協働し、緩和ケアも含めて患者と家族の生活を支える
。 - 急変時の対応: 在宅療養者の容体が急変した際の、往診や訪問看護、入院病床の確保体制
。 - 看取り: 住み慣れた自宅や施設など、患者が望む場所での看取りの実施
。
これらの機能を地域全体で実現するためには、もはや個々の医療機関や介護事業所の努力だけでは不可能です。資料で示されている福井県や長野県駒ヶ根市の先進事例のように、ICT(情報通信技術)を活用して基幹病院と地域の診療所、訪問看護ステーション、薬局、そして介護施設がリアルタイムで患者情報を共有し、一体となって支える体制の構築が不可欠となります
この連携の輪の中に、皆様が経営される医療機関や社会福祉法人が、中心的なプレイヤーとして位置づけられているのです。
法人経営者が今、具体的に考えるべきこと
この大きな変革の波は、私たちの法人経営にどのような影響を与え、何を問いかけているのでしょうか。
医療機関に求められる役割の再定義
従来のピラミッド型の医療提供体制は、機能ごとの連携を前提としたネットワーク型へと変わります。例えば、山形県米沢市の事例では、地域の中核病院が急性期医療に特化・集約し、もう一方の民間病院が回復期・慢性期を担うという、明確な機能分化と連携によって、持続可能な救急医療体制を再構築しました
自院の強みはどこにあるのか。「急性期拠点機能」を担うのか、あるいは高齢者救急を受け入れ在宅復帰を支える「高齢者救急・地域急性期機能」を担うのか
社会福祉法人に高まる期待と責任
「介護との連携」が構想の柱に据えられたことで、社会福祉法人の役割は、これまで以上に重要性を増します
- 医療ニーズの高い入所者をどこまで受け入れるか?
- 地域の病院や在宅クリニックと、どのような情報連携・協力体制を築くか?
- 看取りまでを視野に入れたケアを提供できる職員のスキルアップをどう図るか?
これらの問いにどう答えるかが、法人の将来性を大きく左右するでしょう。
職員の働き方と育成(人事労務の視点)
この変革は、現場で働く職員の働き方や求められるスキルにも大きな変化をもたらします。医師偏在対策や働き方改革と一体で進められるこの構想は、法人内の人事戦略にも影響を与えます
多職種連携が当たり前になる中で、コミュニケーション能力や他職種への理解が深い人材の価値は飛躍的に高まります。また、在宅医療・訪問看護のニーズ増大は、看護師や介護職員の採用・定着・育成戦略の見直しを迫ります
おわりに:未来を創るための対話と準備
今回ご紹介した「新しい地域医療構想」は、2040年に向けた日本の医療・介護提供体制の方向性を決める、極めて重要な取り組みです。2040年はまだ先のことと感じられるかもしれませんが、その基本設計に関する議論はすでに始まっています。
この大きな変化は、各法人にとって適応が求められる挑戦であると同時に、地域社会における自法人の役割を再確認し、新たな価値を創造する好機とも捉えられます。
最も重要なのは、国が示す大きな方向性を正確に把握し、地域の他の医療機関や介護事業者との連携を見据え、今から準備を始めることです。本稿が、地域の医療・介護を支える皆様にとって、今後の事業展開を考える上での一助となれば幸いです。
【参考サイト】第116回社会保障審議会医療部会
【参考資料】第116回社会保障審議会医療部会 資料1 地域医療構想、医師偏在対策等の検討体制について