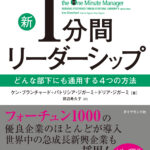精神疾患の労災認定1,000人超え。経営者が今すぐ取り組むべき「カスハラ」「パワハラ」対策とは?
先日、厚生労働省から2024年度に精神疾患が原因で労災認定された方が、ついに1,000人を超え、1,055人に達したという報告がなされました。これは前年度から172人も増加しており、6年連続で過去最多を更新するという極めて深刻な事態です。
【参考リンク】厚生労働省
特に、医療施設や介護・障害福祉事業所、そして日々奮闘されている中小企業の経営者や人事担当者の皆様にとって、これは決して対岸の火事ではありません。大切な従業員を守り、持続可能な経営を実現するために、今、何をすべきなのか。本コラムでは、最新の動向を専門家の視点で分析し、具体的な対策を提言します。
深刻化する職場のメンタルヘルス – 統計データが示す現実
今回の発表で注目すべきは、単に労災認定者数が増加したという事実だけではありません。その「原因」にこそ、現代の職場が抱える根深い問題が映し出されています。
労災認定の主な原因 – 職場に潜む4つの脅威
労災認定に至った精神疾患の原因を見てみると、以下のようになっています。
- 上司等からのパワーハラスメント:224人
- 仕事内容・仕事量の(大きな)変化:119人
- 顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント):108人
- セクシュアルハラスメント:105人
長年、職場におけるメンタルヘルスの大きな要因であった「パワハラ」が依然として最多であることに加え、今回特に警戒すべきは「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の急増です。その数は前年度から倍増し、セクハラを上回る第3位の原因となりました。
医療や介護・福祉の現場では、利用者様やそのご家族との密なコミュニケーションが不可欠です。
しかし、その関係性の中で、心無い言葉や理不尽な要求、時には暴力といった過酷なハラスメントに、職員が疲弊していくケースが後を絶ちません。
「人の役に立ちたい」という高い志を持って入職した職員が、心身をすり減らし、休職や離職に追い込まれる現実は、事業所のサービス品質低下に直結するだけでなく、経営基盤そのものを揺るがしかねない重大なリスクです。
国も動いた!労災認定基準の改正と企業の責任
こうした状況を受け、国も対策を強化しています。2023年9月1日、厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」を改正しました。
【参考リンク】厚生労働省
この改正は、経営者や人事担当者が必ず押さえておくべき重要なポイントを含んでいます。
改正のポイント①:「カスタマーハラスメント」の明記
最大の変更点は、労災認定の判断材料となる「具体的出来事」の項目に、「顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)」が明確に追加されたことです。 これまでも「顧客とのトラブル」は評価の対象でしたが、より具体的にカスハラの実態に即した評価が可能となりました。
これは、国がカスハラを「業務に起因する重大なストレス要因」として正式に認めたことを意味します。
これにより、今後、従業員がカスハラを原因として精神疾患を発症した場合、企業の安全配慮義務違反がより厳しく問われる可能性が高まったと言えるでしょう。
改正のポイント②:パワハラの具体例を網羅
パワハラの6類型(①身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害)について、それぞれの具体例がより詳細に示されました。これにより、「これは指導か、パワハラか」といったグレーゾーンの判断が、より客観的な基準で行われるようになります。
すべての事業主に課せられた「ハラスメント防止措置義務」
忘れてはならないのが、2022年4月から、パワーハラスメント防止措置がすべての事業主(中小企業を含む)に義務化されているという事実です。セクハラやマタハラと合わせ、企業はハラスメントに対して断固として対応する体制を構築する法的責任を負っています。今回の労災認定者数の増加と認定基準の改正は、この義務の重要性を改めて浮き彫りにしたと言えます。
企業に求められる具体的な対策 – リスク回避から価値創造へ
では、企業は具体的に何から手をつければよいのでしょうか。法的な義務を果たすことはもちろん、従業員が安心して働ける環境を整備するための具体的なステップを以下に示します。
ステップ1:防止方針の明確化と社内への周知・啓発
就業規則への明記: 職場におけるハラスメントを一切許さないという方針を明確に示し、ハラスメントの定義、禁止行為、懲戒規定などを就業規則に具体的に盛り込みます。
経営トップからのメッセージ発信: 経営者が自らの言葉で、ハラスメント撲滅への強い意志を全従業員に伝えることが極めて重要です。朝礼や社内報などを活用し、繰り返し発信しましょう。
研修の実施: 管理職向け、一般職員向けに、それぞれの立場に応じたハラスメント研修を定期的に行います。特に管理職には、部下からの相談に適切に対応する「傾聴力」や、ハラスメントの芽を早期に発見する能力が求められます。
ステップ2:相談しやすい体制の構築
相談窓口の設置: 人事部だけでなく、信頼できる第三者(例えば、当事務所のような外部の専門家)を含めた複数の相談窓口を設置し、従業員が安心して相談できる選択肢を確保します。相談者のプライバシー保護は絶対に遵守されなければなりません。
カスハラ対応マニュアルの作成: 「どのような行為がカスハラにあたるのか」「現場でカスハラに遭遇した場合、誰に、どのように報告・相談するのか」「組織としてどのように対応するのか(毅然とした対応、警察等との連携)」といった具体的な対応手順をマニュアル化し、全職員で共有します。これにより、職員は一人で抱え込むことなく、組織として対応できるという安心感を得られます。
ステップ3:事後の迅速かつ適切な対応
事実関係の調査: 相談があった場合、プライバシーに配慮しつつ、双方から迅速かつ正確に事実確認を行います。
被害者への配慮と加害者への厳正な措置: 調査結果に基づき、被害を受けた従業員のメンタルケアや就業場所の変更など、適切な配慮措置を講じます。一方、加害者に対しては、就業規則に基づき厳正に対処します。社内での解決が困難な場合は、弁護士などの専門家と連携することも必要です。
【当事務所の見解】職場のメンタルヘルス対策は、もはやリスク管理ではなく「経営戦略」である
ここまで、最新のデータと法改正に基づき、企業が取るべき対策を解説してきました。しかし、当事務所が最もお伝えしたいのは、これらの対策を単なる「やらされ仕事」や「コストのかかるリスク管理」として捉えないでほしい、ということです。
人材不足が叫ばれて久しい日本において、特に専門性が高く、人の温かさがサービスの質に直結する医療・介護・福祉の現場では、「人」こそが最も重要な経営資源です。
一人の優秀な職員、経験豊富な職員が心を病み、職場を去っていくことの損失は、計り知れません。
それは、単に欠員を補充すれば済む話ではないのはないでしょうか。
残された職員の負担増、チームワークの乱れ、ひいてはサービスの質の低下を招き、利用者やその家族からの信頼を失うという負のスパイラルに陥りかねません。
従業員の心の健康を守るための投資は、決してコストではありません。それは、未来に向けた最も確実な「投資」です。
従業員が
「この職場は、いざという時に自分を守ってくれる」
「ここでは安心して自分の意見が言える」
と感じられる環境、すなわち「心理的安全性」の高い職場は、ハラスメントのリスクが低いだけでなく、従業員の定着率を向上させます。
それだけではありません。職員一人ひとりが萎縮することなく、持てる能力を最大限に発揮し、より良いサービスを提供しようと自発的に考え、行動するようになります。職員同士の円滑なコミュニケーションは、新たな気づきや業務改善のアイデアを生み出す土壌となるでしょう。
つまり、従業員のメンタルヘルスを守ることは、離職率の低下や採用コストの削減といった「守り」の効果だけでなく、サービスの質の向上、顧客満足度の向上、そして企業の持続的な成長といった「攻め」の経営効果を生み出す、強力なエンジンとなり得るはずです。
法律で定められたから対応する、という受け身の姿勢から脱却し、従業員の心の健康を経営の中心課題として捉え、戦略的に職場環境をデザインしていく。その視点の転換こそが、数多ある競合の中から選ばれ、厳しい時代を勝ち抜いていくための、最も本質的な鍵であると当事務所は確信しています。
当事務所は、労働法務の専門家として、就業規則の整備やハラスメント研修といった法的なサポートはもちろんのこと、皆様の事業所に眠る「人」という価値を最大化し、真に強く、しなやかな組織を共に創り上げていくパートナーでありたいと考えています。
何から手をつけて良いかわからない、自社の取り組みが十分か不安だ、という経営者の皆様。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
【参考リンク】厚生労働省
【参考リンク】厚生労働省