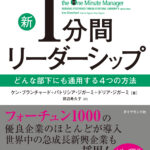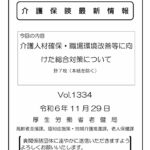令和7年改正労働施策総合推進法に関するリーフレットが公表
6月11日、厚生労働省は、「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下、労働施策総合推進法)等の一部改正について」のページを開設し、関係資料を公開しました。
今回の改正は、単なる制度の修正ではありません。働きやすい職場づくりへの“社会的圧力”が、より一層現場レベルにまで及んできたことを意味します。特に、介護・医療・福祉分野においては、現場職員のストレスや離職の背景にあるハラスメント問題が、以前にも増して深刻化しており、見過ごすことはできません。
「ハラスメントは、もう“あったこと”では済まされない」
ある介護施設の例を挙げましょう。利用者の家族から毎週のように職員へ「対応が悪い」と一方的に電話が入り、実際には丁寧な対応をしていたにもかかわらず、言葉の端々に威圧的な要求が続きました。相談を受けた施設長は「これ以上波風を立てたくない」と我慢を選びましたが、その職員はやがて心身に不調をきたし、退職してしまったのです。
今回の改正では、このような“顧客等による言動”=カスタマーハラスメントについて、事業主が具体的な対策を講じることが義務化されます。これは施設経営者・管理者にとって、明確な責任が課される時代が始まったことを意味します。
改正のポイント①:カスタマーハラスメント対策の義務化
カスハラの定義と対応義務
リーフレットでは、カスタマーハラスメントを以下のように定義しています。
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
③労働者の就業環境を害すること
こうした言動が確認された場合、事業主には次のような対応が求められます。
- 方針の明確化と職員への周知・啓発
- 相談窓口の整備と対応フローの構築
- 実際のトラブル発生時の迅速な対応と再発防止策
つまり、「何かあったときに考える」では遅く、今この段階で、明文化と実装の準備をしておかなければ、経営リスクになりかねないのです。
改正のポイント②:求職者等に対するセクハラ防止措置の義務化
インターンも“職場の一員”
「うちは中途採用だけだから関係ない」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この改正では“求職者等”が対象となっており、これは就職活動中の学生やインターンシップ生なども含まれます。
たとえば、面接時に不用意にプライベートに踏み込んだ質問をしたり、職場見学で不適切な接触があった場合、それがセクハラと見なされる可能性があるのです。
対策として事業主に求められるのは、以下のような措置です。
- 面談時等のルールを明確化し、文書で周知
- 専用の相談体制の整備
- 被害申告時の謝罪・対応・再発防止の徹底
改正のポイント③:女性活躍推進に関する新要件
情報開示義務の拡大
これまで従業員301人以上の企業に限られていた「男女間賃金差異」の情報公開義務が、101人以上の企業にも拡大されました。さらに「女性管理職比率」もあわせて公開が求められます。
医療・福祉分野では、女性職員の割合は高くても、管理職に占める女性の割合は少ない――という構造がしばしば見られます。この点の“見える化”は、今後、施設の評価や採用力に影響を及ぼす可能性が高まります。
プラチナえるぼしの要件変更
厚労省が認定する「プラチナえるぼし」の認定要件にも、新たに「求職者等に対するセクハラ防止の取組内容を公表していること」が追加されました。すでに認定を受けている法人も、今後は更新時に対応が求められることになります。
「指針を待ってから考える」では遅い
今回の改正では、「具体的な措置内容は今後、指針により示す予定」とされています。しかし、これを「まだ動かなくてもいい」と受け取るのは危険です。
なぜなら、トラブルが起きたときに「準備していなかった」では済まされず、「すでに公表されていた改正内容に基づく予見可能性」が問われる可能性があるからです。
特に、介護施設や医療機関では利用者や家族との接点が日常的にあり、ハラスメントに発展するリスクは高い現場です。対応体制の整備が遅れれば、それだけ現場職員の離職や訴訟といった“回避可能な損失”を生み出すことになりかねません。
今回の法改正は、公布後1年6か月以内の政令で定める日に施行される予定で今後の法整備によって具体化される見込みです。しかし、対応が求められる義務の中身はすでに明文化されつつあり、「準備期間」は始まっています。
厚労省は今後、ガイドラインや指針を示していくとしていますが、その内容が公表された後に「ゼロから準備」を始めては間に合わない可能性があります。特に、人員配置や研修体制、相談ルートの整備には、予算と時間が必要です。
当事務所では、これまで多くの医療・介護・福祉法人様に対して、就業規則の見直し、ハラスメント防止措置の設計、相談体制の整備などをサポートしてきました。
また、「女性活躍推進法に基づく情報公表の方法がわからない」といった相談にも応じています。
一つひとつの取り組みは小さくても、現場で働く人たちが安心して働ける環境を整えることが、結果として法人の継続的な発展にもつながっていきます。
「気づいた時に、すぐ相談」できる環境を
今回の改正は、事業主の姿勢そのものが問われるものです。制度として義務化されたからではなく、「自分の職場で何ができるか」を考えるタイミングが今だと感じています。
“何から始めたらよいかわからない”という状態も、決して放置せず、まずはご相談いただければと思います。手続きや書面づくりだけでなく、現場のリアリティに即した具体的な運用を一緒に考えてまいります。
ぜひ、貴法人の状況に合わせた実践的な対策を、一緒に設計していきましょう。
【参考サイト】厚生労働省 令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について
【参考資料】労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の公布について(令和7年6月11日基発0611第1号・雇均発0611第1号)
【参考資料】令和7年労働施策総合推進法等一部改正法のポイント