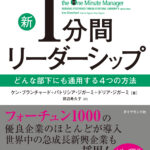「まさか、うちの〇〇さんが…?」
ある日、優秀なベテラン職員のAさんから「親の介護で、どうしても仕事との両立が難しくなりました」と告げられ、頭が真っ白になったと語る理事長がいらっしゃいました。Aさんは、長年組織を支えてきたなくてはならない存在。彼女の突然の退職は、組織にとって大きな痛手となり、残された職員の業務負担増、そして何より、介護離職という「負の連鎖」の始まりを予感させる出来事だったそうです。
これは、決して他人事ではありません。少子高齢化が急速に進む日本において、介護は「いつか誰にでも起こりうる」身近な問題となりました。特に、医療・福祉の現場では、人材不足が慢性化し、一人ひとりの職員にかかる負担は増す一方です。そんな中、介護による離職は、組織の安定した運営を根底から揺るがしかねない深刻なリスクとなりつつあります。
令和7年6月5日、「令和6年育児・介護休業法改正を踏まえた実務的な介護両立支援の具体化に関する研究会(第3回)」が開催され、「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール たたき台(案)」が示されました。これは、単なる法律の変更点リストではありません。介護離職を防ぎ、職員が安心して働き続けられる環境をどう構築していくか、その実践的なヒントと具体的な道筋を示す羅針盤となるものです。
今回のコラムでは、この「たたき台(案)」の内容を深掘りし、介護両立支援の具体的な対策について、事例と共にご紹介します。
なぜ今、介護両立支援が急務なのか? 組織の未来を左右する静かなる波
「介護離職」という言葉を聞いて、「うちの職員は大丈夫だろう」「まだ先の話だ」と考えてはいませんか?厚生労働省の資料によると、介護をしながら仕事をする労働者数は約365万人、家族の介護・看護を理由とする離職者数は年間約10.6万人にも上ると報告されています。
特に50歳から64歳の層で多く、これはまさに組織の中核を担うベテラン職員の層と重なります。
予測不能な「介護の始まり」が、組織の安定を脅かす
育児と異なり、介護はいつ始まり、いつまで続くか、正確に予測することが非常に難しいという特性があります。ある日突然の病気や事故、あるいは認知症の進行など、予期せぬ形で介護が始まることは少なくありません。
例えば、ある病院の看護師長Bさんは、いつも元気で責任感も強く、若手看護師の育成にも尽力していました。しかし、ある日、遠方に住むご両親が相次いで倒れ、急遽実家に帰省することに。数週間後、Bさんは病院に戻りましたが、心ここにあらずといった様子で、業務中のミスが増え、チーム全体の士気にも影響が出始めました。「遠距離介護なので、週末だけ実家に帰るのですが、その往復と介護で心身ともに疲弊してしまって…」と、後日打ち明けてくれました。結局、Bさんは看護師長という要職を辞し、配置転換となりましたが、彼女の抜けた穴は大きく、組織全体に動揺が走ったそうです。
このような時、組織として適切な支援がなければ、Bさんのように心身のバランスを崩し、最悪の場合、離職という選択をせざるを得なくなる職員が増えてしまいます。介護による離職は、単に一人の職員が減るだけでなく、他の職員の業務負担増、モチベーション低下、そして組織全体の生産性低下に直結する深刻な問題なのです。
中核人材の流出が、組織の未来を危うくする
特に社会福祉法人や医療機関では、専門性の高い職員が多く、一人ひとりの知識や経験が組織の財産です。ベテラン職員が介護を理由に離職することは、長年培ってきたノウハウの喪失、新たな人材の育成コスト、そして何より、組織全体のサービスの質の低下を招きます。
「介護離職」は、個人のキャリアを中断させるだけでなく、組織の持続的な成長を阻害する「人的資本経営」における重要なリスクマネジメント課題として認識すべきです。
令和6年育児・介護休業法改正が示す、新たな羅針盤
今回の法改正は、まさにこの「介護離職」問題に警鐘を鳴らし、企業に具体的な対策を求めています。単なる制度の拡充に留まらず、企業がより積極的に、そして実効性をもって介護両立支援に取り組むことを促すものです。
「たたき台(案)」では、介護両立支援を3つのステップに分けて、それぞれの場面で企業が具体的に「何をすべきか」を明確に示しています。
STEP1:前もって実施しておくべきこと|「まさか」を「もしも」に変える意識改革
介護は、突然始まるからこそ、事前に準備しておくことが非常に重要です。このステップでは、介護に直面する前から、組織全体で介護両立支援に対する意識を高め、職員が安心して相談できる環境を整備することが求められています。
具体的な取組例
- 研修の実施: 介護保険制度や会社の介護両立支援制度について、全職員を対象とした研修を実施します。単なる制度説明に終わらず、「自分は介護しすぎない」「仕事と介護の両立は可能だ」といった意識を醸成することが重要です。また、管理職には、介護に直面した職員の状況を把握し、適切な支援ができるよう、マネジメント視点を取り入れた研修も有効です。
- 相談窓口の設置と周知: 職員が気軽に相談できる窓口を設置し、その存在を周知徹底します。プライバシーに配慮し、人事部だけでなく、各部署の管理職や外部の専門家(社会保険労務士など)も相談員となることで、より多様なニーズに対応できる体制を構築します。
- 利用事例の収集・提供: 実際に仕事と介護を両立している職員の事例(ロールモデル)を収集し、社内で共有します。成功事例だけでなく、どのような課題に直面し、どう乗り越えたのかといったリアルな経験を伝えることで、他の職員が具体的なイメージを持てるようになります。
- 両立支援方針の周知: 経営層から、職員の就業継続を後押しする強いメッセージを発信し、介護両立支援が会社の重要な方針であることを明確にします。社内報やイントラネット、朝礼などを活用し、継続的に周知していくことが効果的です。
トラブル事例
ある介護施設では、「介護は個人の問題」という意識が根強く、介護両立支援制度は存在するものの、ほとんど利用されていませんでした。ある時、ベテランの介護士Cさんが、認知症の母親の介護で心身ともに疲弊し、業務中に集中力を欠く場面が増え始めました。同僚は異変に気づいていましたが、Cさんが「大丈夫です」としか言わず、また、相談できる雰囲気もなかったため、誰も介入できませんでした。結果、Cさんは重大な介護事故を起こしかけ、精神的に追い詰められ、退職してしまいました。もし、早い段階でCさんが相談できる環境があり、適切な支援を受けられていれば、このような事態は防げたかもしれません。
STEP2:社員が40歳になったら|介護を「自分事」と捉えるきっかけづくり
40歳前後は、介護保険料の徴収も始まり、親の健康状態に変化が見られるようになる時期です。しかし、まだ介護が「自分事」として捉えられていない職員も少なくありません。このステップでは、この「40歳」という節目を活用し、介護をより身近な問題として認識させるための情報提供を行います。
具体的な取組例
- 介護保険制度の基礎知識提供: 40歳に到達する職員に対して、介護保険制度の仕組み、介護サービスの種類、利用方法などを分かりやすく説明します。厚生労働省が作成しているリーフレットや動画などを活用することも有効です。
- セルフチェックシートの活用: 自身の親の健康状態や、将来的な介護リスクについて、簡単なセルフチェックができるシートを配布します。これにより、職員が「もしかしたら自分にも関係するかもしれない」と介護を自分事として捉えるきっかけを作ります。
- シミュレーション研修: 「もし今夜、親が倒れたら?」といった具体的なシミュレーションを通じて、介護が始まった際の仕事と生活への影響を具体的にイメージさせ、事前準備の重要性を認識させます。
トラブル事例
ある病院の事務職員Dさんは、40歳を過ぎてもご両親は健在で、介護についてほとんど考えていませんでした。ある日、実家に住む母親が突然倒れ、入院することに。入院手続きや今後の介護について、何から手をつけて良いか分からず、病院の事務局に相談しましたが、「それは個人で対応することです」と言われ、途方に暮れてしまいました。結局、Dさんは自身の有給休暇をすべて使い果たし、さらに無給休暇を取らざるを得なくなり、経済的にも精神的にも追い詰められました。もし、Dさんが40歳になった時点で、介護に関する情報提供を受け、「親が元気なうちに把握しておくべきこと」について知識があれば、ここまで追い詰められることはなかったでしょう。
STEP3:社員から家族介護に直面したと言われた|最後の砦としての個別支援
実際に職員から介護に直面したという申出があった場合は、これが介護離職を防ぐための「最後の砦」となります。この段階では、個々の職員の状況や希望を丁寧にヒアリングし、制度利用の意向確認を行い、最適な両立支援策を共に検討することが求められます。
具体的な取組例
- 丁寧なヒアリングと意向確認: 介護に直面した職員の状況(要介護者の状態、同居・別居、介護分担など)や、仕事と介護の両立に関する希望を丁寧にヒアリングします。その際、制度の利用意向や、どのような働き方を希望しているかを具体的に確認します。
- 制度の趣旨説明と活用促進: 介護休業や介護休暇などの制度について、その趣旨を理解した上で、利用を促進します。特に、介護休業は「介護に専念するため」ではなく、「介護の体制を整えるための準備期間」であることを明確に伝えます。
- 介護サービスの活用支援: 介護保険サービスや民間サービスなど、利用可能な介護サービスについて情報提供し、職員が「自分で介護しすぎない」ように促します。必要に応じて、ケアマネジャーとの連携を支援し、適切なケアプラン作成をサポートします。
- 働き方の調整: 時短勤務や時差出勤、フレックスタイム制、在宅勤務など、多様な働き方を組み合わせることで、仕事と介護の両立を可能にするための柔軟な対応を検討します。
- プライバシー保護の徹底: 介護に関する情報は非常にデリケートであるため、職員のプライバシー保護を徹底し、安心して相談できる環境を維持します。
トラブル事例
ある社会福祉法人のベテラン介護士Eさんは、父親の介護が始まり、介護休業の取得を検討していました。上司に相談したところ、「介護休業を取ると、他の職員に迷惑がかかるし、評価にも響くよ」と言われ、結局介護休業の取得を諦め、無理をして働き続けました。しかし、介護疲れから体調を崩し、最終的には休職に追い込まれ、そのまま退職してしまいました。このような「ケアハラスメント」は、介護離職を加速させる要因となります。介護に直面した職員に対して、組織全体で温かいサポートを提供し、安心して制度を利用できる職場風土を醸成することが何よりも重要です。
組織全体の意識改革が、介護両立支援の鍵を握る
ここまで、具体的なステップと取組例をご紹介してきましたが、最も大切なのは、組織全体の意識改革です。介護両立支援は、単に個々の職員を支援するだけでなく、「お互い様」の精神で支え合い、多様な働き方を認め合う職場風土を醸成することに他なりません。
管理職の役割と、コミュニケーションの重要性
管理職は、介護両立支援において非常に重要な役割を担います。職員の介護状況を把握し、適切な情報提供や制度利用の促進、そして何よりも、職員が「困ったときに安心して相談できる」関係性を日頃から築いておくことが求められます。
「うちの課長は、いつも『何かあったらすぐに相談してくれ』と言ってくれるので、本当に心強いです」と語る職員の声は、管理職の意識一つで、職場の雰囲気が大きく変わることを示しています。定期的な個別ミーティングなどを通じて、職員の状況を把握し、潜在的な介護リスクを早期に発見することも重要です。
普段からの「働きやすい職場環境」づくりが、介護離立を防ぐ土台
介護両立支援は、特別なことではありません。普段から有給休暇を取得しやすい環境を整えたり、残業時間を厳しく管理したり、テレワークなどの柔軟な働き方を推奨したりといった、「働きやすい職場環境」づくりが、そのまま介護両立支援の土台となります。
「うちの会社は、普段から休みやすい雰囲気なので、介護が始まった時も、ためらいなく有給を使えました。それが本当に助かりました」という職員の声は、日頃からの小さな取り組みが、いざという時に大きな支えとなることを物語っています。
「たたき台(案)」から読み解く、今すぐ手に入れるべき「支援ツール」
今回の「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール たたき台(案)」で示された「利用可能な様式等」は、貴社が介護両立支援を具体的に進める上で、すぐに活用できる実践的なツール集です。これらのツールを導入し、適切に運用することで、職員の介護に関する不安を軽減し、組織全体の対応力を高めることができます。
「仕事と介護の両立準備ガイド」で、漠然とした不安を解消する
多くの職員は、介護に対して漠然とした不安を抱えています。「いつか親の介護が始まったら、自分はどうなるんだろう」「仕事との両立なんて本当にできるのだろうか」といった声は少なくありません。この漠然とした不安を具体的に解消するために、「仕事と介護の両立準備ガイド」は非常に有効なツールとなります。
ガイドには、介護保険制度の基礎知識、利用できる介護サービスの種類、そして介護が始まった際の具体的な手続きなどが網羅されています。これを職員に配布し、事前に目を通してもらうことで、「もしも」の時にどうすれば良いのか、ある程度の見通しを持つことができます。これにより、職員は安心して仕事に集中でき、いざ介護に直面した際も、冷静に対応するための第一歩を踏み出せるようになります。
「面談シート兼介護両立支援プラン」で、個別支援を形にする
介護は、一人ひとり状況が異なります。画一的な対応では、真に職員を支えることはできません。そこで力を発揮するのが、「面談シート兼介護両立支援プラン」です。これは、職員が介護に直面した際に、上司や人事担当者との面談を通じて、個別の状況を詳細に把握し、最適な両立支援プランを共に作り上げるためのシートです。
「面談シート」には、要介護者の状態、同居・別居の状況、他の家族の介護分担、そして本人の仕事と介護の両立に関する希望などが記載されます。これにより、担当者は職員の抱える課題を具体的に理解し、介護休業や介護休暇の取得、時短勤務、テレワーク導入など、多様な選択肢の中から最適な解決策を提案することができます。
ある医療法人では、この面談シートを導入したことで、職員の介護に関する潜在的なニーズを掘り起こすことができました。ある理学療法士のFさんは、当初、親の介護で退職を考えていましたが、面談シートを使って上司と話し合う中で、時短勤務と外部の介護サービスを組み合わせることで、仕事と介護の両立が可能になることに気づきました。「一人で抱え込んでいた時は絶望的でしたが、面談シートに書き出すことで、課題が整理され、解決策が見えてきました」とFさんは語っています。
「ケアマネジャーに相談する際のチェックリスト」で、専門家との連携を円滑に
介護の世界は、専門用語も多く、複雑に感じられるかもしれません。特に、介護サービスの要となるケアマネジャーとの連携は、介護両立支援の成否を分ける重要なポイントです。
「ケアマネジャーに相談する際のチェックリスト」は、職員がケアマネジャーと面談する際に、伝えるべき情報や確認すべき事項をまとめたものです。これにより、職員は限られた時間の中で効率的に情報を伝え、必要な介護サービスをスムーズに導入することができます。
また、企業側から見ても、職員がケアマネジャーと円滑に連携できることは、介護休業や介護休暇の期間を短縮したり、介護による業務への影響を最小限に抑えたりすることに繋がります。これは、結果として組織の生産性維持にも貢献すると言えるでしょう。
「相談できない…」〜見えないリスクとコスト
ここまで、介護両立支援の重要性と具体的な対策についてお話ししてきました。しかし、最も避けなければならないのは、「相談しない」「相談できない」という選択です。職員が介護の悩みを一人で抱え込み、誰にも相談しないまま無理を続けることは、組織にとって計り知れないリスクとコストに繋がります。
介護休業の取得経験者が、介護が始まった当初は一人で抱え込んでしまい、「もっと早く相談すればよかった」と感じていることもよく耳にします。多くの職員が、介護について相談することへの心理的ハードルを感じているのではないのでしょうか。
優秀な人材の「サイレント離職」
介護の悩みを抱えながらも相談できない職員は、次第に心身のバランスを崩し、パフォーマンスが低下していく可能性があります。このような状態が続くと、最終的には「サイレント離職」、つまり、誰にも相談しないまま、静かに退職の準備を進め、ある日突然、組織から姿を消してしまうという事態に繋がりかねません。特に、介護は非常に個人的な問題であるため、周囲に知られたくないと考える職員も少なくありません。
「あの人は最近、元気がないな」「どうも集中できていないようだ」といった兆候に気づいても、原因が分からず、どう声をかけて良いか分からないという状況は、組織にとって大きな機会損失です。サイレント離職は、予期せぬ形で組織の人的資源を失うだけでなく、残された職員の業務負担を急増させ、組織全体の士気を著しく低下させます。
顕在化する「介護ハラスメント」のリスク
残念ながら、介護両立支援の理解が不十分な職場では、「介護ハラスメント(ケアハラ)」が起こる可能性も否定できません。これは、介護を理由とする不当な言動や、制度利用への妨害など、職員が介護に関する悩みを相談しにくい雰囲気を作り出してしまうことです。
例えば、「介護休業を取ると、他の職員に迷惑がかかる」「介護なんて個人的な問題だ」といった発言は、介護ハラスメントに該当する可能性があります。このような言動は、職員のエンゲージメントを著しく低下させ、組織への不信感を募らせる原因となります。最悪の場合、法的なトラブルに発展し、組織のブランドイメージを損なうことにも繋がりかねません。
組織の生産性低下と、見えない経済的損失
介護の悩みを抱えた職員は、集中力の低下や疲労から、業務効率が落ち、ミスが増える傾向にあります。これは、組織全体の生産性低下に直結するだけでなく、医療・福祉の現場においては、利用者や患者様へのサービス提供の質にまで影響を及ぼしかねません。
また、介護離職が発生すれば、新たな人材の採用・育成に多大なコストがかかります。求人広告費、採用活動にかかる時間、そして新人教育にかかる費用など、目に見えるコストだけでも決して少なくありません。さらに、長年培ってきたベテラン職員の知識やノウハウが失われることによる、見えない損失は計り知れません。
今こそ、専門家と共に「介護と仕事の両立支援」の未来を切り拓く時
「令和6年育児・介護休業法改正を踏まえた実務的な介護両立支援の具体化に関する研究会」で示された「たたき台(案)」は、介護両立支援に本格的に取り組む法人に対しては、強い後押しとなるでしょう。しかし、法律の条文を読み解き、自社の状況に合わせて制度を構築し、職員に周知徹底し、そして何よりも「人」の心を動かす実践的な支援を実現するためには、専門的な知識と経験が必要です。
当事務所は、労働法、介護保険法、医療法の専門知識を持つ社会保険労務士として、社会福祉法人や医療機関の皆様が直面する介護両立支援の課題に対し、きめ細やかなサポートを提供しています。
- 法改正への対応支援: 複雑な法改正の内容を分かりやすくご説明し、貴社の就業規則や社内規定を、新たな法律に則して整備します。
- オーダーメイドの制度設計: 貴社の組織規模、職員の年齢構成、事業内容、そして組織の風土などを詳細に分析し、最も効果的な介護両立支援制度をオーダーメイドで設計します。
- 研修・セミナーの実施: 経営層から管理職、一般職員まで、それぞれの立場に応じた研修・セミナーを実施し、介護両立支援に関する知識と意識を向上させます。
- 相談窓口の設置・運用支援: 職員が安心して相談できる窓口の設置をサポートし、プライバシーに配慮した運用体制を構築します。必要に応じて、外部相談窓口の活用もご提案します。
- 介護ハラスメント対策: 介護ハラスメントの発生を未然に防ぐための研修や、発生時の適切な対応方法についてアドバイスします。
「このままだと、何か組織にとって大きな問題が起こるかもしれない」
もし、貴社がそう感じられているなら、それは、まさに今が「行動の時」であることを示しています。
介護両立支援は、単なるコストではありません。それは、貴社が職員を大切にし、社会的な責任を果たす企業であることを示す、未来への投資です。そして、その投資は、職員のエンゲージメント向上、離職率の低下、生産性の向上、そして組織の持続的な成長という形で、必ず貴社に還元されるでしょう。
貴社の組織の未来を守り、職員が心身ともに健康で、長く活躍できる職場環境を共に創り上げていくために直面している課題を、当事務所の専門家と一緒に解決しませんか?組織の未来を守るために、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。