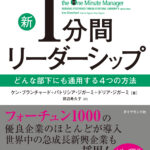令和7年度介護保険部会より|介護事業経営者が今すぐ知るべき「2040年問題」への処方箋
 「うちの施設も、いよいよ人手不足が深刻でね…」
「うちの施設も、いよいよ人手不足が深刻でね…」
「日々の業務に追われて、新しい制度改正なんて、正直キャッチアップしきれないよ…」
クリニックや介護施設の経営者様、人事・労務ご担当者様から、このような悲痛な叫びをお聞きする機会が後を絶ちません。皆様、日々のオペレーションに加えて、絶え間ない制度変更への対応、そして何よりも深刻な人材不足という大きな課題に直面されていることと存じます。
先日、令和7年5月19日に開催された第120回社会保障審議会介護保険部会では
差し迫る「2040年問題」を見据え、介護サービス提供体制の持続可能性をどう確保していくのか。今回の部会で示された方向性は、今後の皆様の事業経営に直結する極めて重要な内容と言えるでしょう。
本コラムでは、社会保険労務士の視点から、今回の介護保険部会のポイントを分かりやすく解説し、経営者の皆様が今すぐ取り組むべきこと、そして私たち専門家がどのようにお力になれるのかをお伝えします。
※本記事に登場する人物・企業名。事例については、すべてプライバシー保護の観点から架空のものです。ただし、記載されている事例は、当事務所が実際に経験した複数のケースを基に再構成したものであり、その本質は実際の経験に基づいています。
忍び寄る危機「2040年問題」と介護保険部会の役割
ご存知の通り、我が国は急速な少子高齢化の真っただ中にあります。特に、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年には、高齢者人口がピークを迎える一方で、生産年齢人口は大幅に減少すると予測されています。介護ニーズが爆発的に増加するにもかかわらず、介護の担い手はますます不足するという、まさに国難とも言える状況です。
このような背景のもと、社会保障審議会介護保険部会では、介護保険制度の円滑な運営と持続可能な提供体制の構築に向けた議論が重ねられています。今回の第120回部会も、「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会の中間とりまとめを踏まえ
他人事では済まされない、この国の大きな変化の波。その最前線で地域社会を支える皆様にとって、部会の議論は、事業継続のための羅針盤となるはずです。
【最重要ポイント解説】第120回介護保険部会から読み解く経営課題
今回の部会資料は多岐にわたりますが、特に経営者の皆様に押さえていただきたい主要な論点は以下の通りです。
待ったなし!介護人材の確保と定着への多角的アプローチ
もはや「最大の課題」と明言されている介護人材の確保
- 処遇改善の継続と実態把握の重要性:全産業平均の賃金動向を注視しつつ、賃上げ努力を継続する必要性が改めて強調されています
。令和6年度の介護報酬改定では処遇改善加算の一本化と加算率の引き上げが行われましたが 、その効果を検証し、更なる改善につなげていく姿勢が示されました。実際、令和6年度の賃上げ率は全産業平均5.10%に対し、介護事業所平均は2.52%と、まだ乖離があるのが実情です 。 - 多様な人材の確保・育成:若年層への魅力発信強化
、元気な高齢者や他分野からの転職者へのアプローチ 、そして外国人介護人材の受け入れ環境整備と定着支援(特に日本語教育の強化) など、あらゆる角度からの人材確保策が議論されています。特に介護福祉士養成施設における外国人留学生の割合が増加している現状(令和6年度入学生の約半数) を踏まえ、その教育体制の充実も急務です。 - 離職防止・定着支援・生産性向上:ここが今回の大きなポイントです。単に人を増やすだけでなく、いかに働きがいのある、そして働きやすい職場を作るか。魅力的なキャリアパスの構築
、ハラスメント対策の強化 、そして後述するテクノロジー活用による生産性向上を通じた業務負担軽減が不可欠とされています 。 - 地域ごとのプラットフォーム機能の充実:ハローワーク、福祉人材センター、介護労働安定センターといった公的機関の連携強化や、都道府県単位でのプラットフォーム構築が提言されています
。これにより、地域の実情に応じたきめ細やかな人材確保戦略を進めることが期待されます。ある県では、既に福祉人材センターがハローワークや介護労働安定センターと連携し、出張相談や合同就職説明会を実施するなどの成果を上げています 。
【迫りくる危機:人材流出の連鎖】 ある中堅介護施設Aでは、数年前から介護職員の採用が計画通りに進まず、既存職員の負担が増加。日々の業務に追われ、研修機会も十分に確保できない状況が続いていました。そんな中、近隣に新しい施設が開設され、より良い条件を求めて経験のある中堅職員が数名転職。残された職員の負担はさらに増し、職場の雰囲気も悪化。結果として、さらなる離職者を招き、一時は入所者へのサービス提供すら危ぶまれる事態に陥りました。経営者は「まさかうちが…」と頭を抱えるばかりでした。
職場環境改善と生産性向上:テクノロジーと人の力の融合
「うちの施設は小規模だから、大掛かりな設備投資は難しい…」そうお考えの経営者様もいらっしゃるかもしれません。しかし、今回の部会では、事業所の規模に関わらず取り組める生産性向上のヒントが数多く示されています。
- テクノロジー活用の加速化:見守りセンサー、インカム、介護記録ソフト、ケアプランデータ連携システム、さらにはAIを活用した業務効率化など、テクノロジー導入の重要性が改めて強調されました
。特に訪問系や通所サービスにおいても、汎用性の高い介護記録ソフトの普及が重点化されるべきとされています 。実際に、AI訪問スケジュール作成ツールの導入で、スケジュール作成時間が大幅に削減され、訪問介護員としてのサービス提供時間が増加したという実証結果も報告されています 。 - 導入支援の強化:国や都道府県による導入支援(イニシャルコストだけでなくランニングコストへの支援も検討)の継続・充実が求められています
。しかし、テクノロジーを導入していない理由として「導入費用が高額」「維持管理費用が高額」といった声が多いのも事実です 。
- 導入支援の強化:国や都道府県による導入支援(イニシャルコストだけでなくランニングコストへの支援も検討)の継続・充実が求められています
- タスクシフティング/タスクシェアリング(介護助手等の活用):介護職員が専門性の高い業務に集中できるよう、清掃、配膳、ベッドメイキングといった周辺業務を「介護助手」に切り出す動きが加速しています
。これにより、介護職員の負担軽減だけでなく、介護助手の雇用創出にも繋がります。 - 「生産性向上推進体制加算」の新設:令和6年度介護報酬改定で新設されたこの加算は
、テクノロジー導入や業務改善の取り組みを評価するものです。委員会の設置義務化(経過措置あり)も盛り込まれ 、事業所全体で生産性向上に取り組む体制づくりが求められます。 - デジタル中核人材の育成:テクノロジー導入や業務改善を牽引するリーダー人材の育成・配置が急務です
。都道府県のワンストップ相談窓口による伴走支援の強化も期待されています 。 - 科学的介護情報システム(LIFE)の活用推進:LIFEへのデータ提出を要件とする加算が増え、その活用によるケアの質の向上とエビデンスに基づいた介護の実践が一層求められています
。
【テクノロジー導入の落とし穴】 ある医療法人が運営する介護老人保健施設Bでは、業務効率化を目指して最新の見守りシステムを導入しました。しかし、導入前の業務フローの見直しや職員への十分な研修が不足していたため、かえって現場が混乱。アラートが頻繁に鳴り、職員は対応に追われ疲弊。一部のベテラン職員からは「こんなもの使えない」と反発の声も上がり、せっかく導入したシステムが十分に活用されないまま宝の持ち腐れ状態に。経営者は「機械を入れれば何とかなると思っていたが…」と後悔しました。
持続可能な経営へ:経営改善支援と協働・大規模化の促進
介護事業は、公定価格が主な収入源であるなど特殊性はあるものの、人材不足、DX化の遅れ、物価高騰など、多くの中小企業が抱える課題と共通する部分も少なくありません
- 経営情報の「見える化」と活用:令和5年の介護保険法改正により、介護サービス事業者は経営情報を都道府県知事に報告することになりました
。この情報を分析し、事業所支援に活用していく体制づくりが進められています。社会福祉法人については、既にWAM(福祉医療機構)のシステムで財務諸表等が公表されており、分析スコアカードの提供も検討されています 。 - ワンストップ相談窓口と専門家連携:雇用管理、生産性向上、経営改善などを一体的に支援する体制を都道府県単位で構築する必要性が示されています
。これには、地域の公認会計士や中小企業診断士といった専門家の活用も含まれます 。 - 協働化・大規模化の推進:小規模事業者が単独で経営課題を解決することが難しい場合、他事業者との連携・協働(バックオフィス業務の共同化、資材の一括購入、共同研修など)や、M&A等による大規模化も有効な選択肢として提示されています
。社会福祉連携推進法人の活用もその一つです 。実際に、複数の法人が連携して人材採用や研修を共同実施したり、物品の共同購入でコスト削減に成功した事例も出てきています 。
【単独経営の限界と連携のメリット】 地域に根差した小規模な訪問介護事業所Cは、長年、地域住民に手厚いサービスを提供してきました。しかし、経営者の高齢化と後継者不在、そして採用難から事業継続に不安を抱えていました。書類作成や請求業務などの事務作業も経営者自身が夜遅くまで行っている状況でした。そんな時、近隣の同規模事業所から連携の提案が。最初は戸惑いもありましたが、事務部門の共同化や、ヘルパーの空き時間を活用した相互応援体制を組むことで、経営者の負担が大幅に軽減。さらに、共同で研修を実施することで、サービスの質も向上し、ヘルパーのモチベーションアップにも繋がりました。「もっと早く相談すればよかった」と経営者は語ります。
変化の波を乗りこなし、未来を拓くために
ここまで見てきたように、第120回介護保険部会では、介護事業経営を取り巻く環境の厳しさと、それに対応するための具体的な方向性が明確に示されました。人材確保、生産性向上、経営改善――これらは個別の課題ではなく、相互に連携し、一体的に取り組むべきものです。
「うちの施設は大丈夫だろうか…」 「何から手をつければ良いのか分からない…」
もし少しでもこのような不安を感じられたなら、それは決して特別なことではありません。多くの経営者様が同じ悩みを抱えていらっしゃいます。
しかし、ここで立ち止まってしまうわけにはいきません。変化の波は、待ってはくれません。
今回の部会で示された論点や施策の中には、助成金や補助金を活用できるものが数多く含まれています
当事務所では、社会保険労務士として、労働法・社会保険のエキスパートとして、最新の法改正に対応した就業規則の整備や労務管理体制の構築はもちろんのこと、人事評価制度の導入、ハラスメント対策研修の実施、そして生産性向上に向けた職場環境改善のご提案など、多岐にわたるサポートをご提供しております。
特に介護業界においては長年の経験・知見をもとに、処遇改善加算の複雑な要件への対応や、職員の定着に繋がるキャリアパス制度の設計、働き方改革関連法への対応など、専門的な知識が不可欠な場面について数多くサービスを提供してまいりました。
今回の介護保険部会の内容は、いわば国からの「こう変わっていくべき」というメッセージです。このメッセージを正しく読み解き、自院・自施設に最適な形で落とし込み、具体的な行動へと繋げていく。そのプロセスを、ぜひ当事務所と二人三脚で進めていきませんか?
課題が山積している今だからこそ、一人で抱え込まず、外部の力を積極的に活用することが、未来を切り拓く賢明な選択と言えるでしょう。まずは、お気軽にご相談ください。皆様の事業が、これからも地域社会になくてはならない存在として輝き続けるために、当事務所が全力でサポートさせていただきます。
【参考サイト】厚生労働省社会保険審議会(介護保険部会)第120回社会保障審議会介護保険部会
【参考資料】 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制について
【参考資料】介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援について